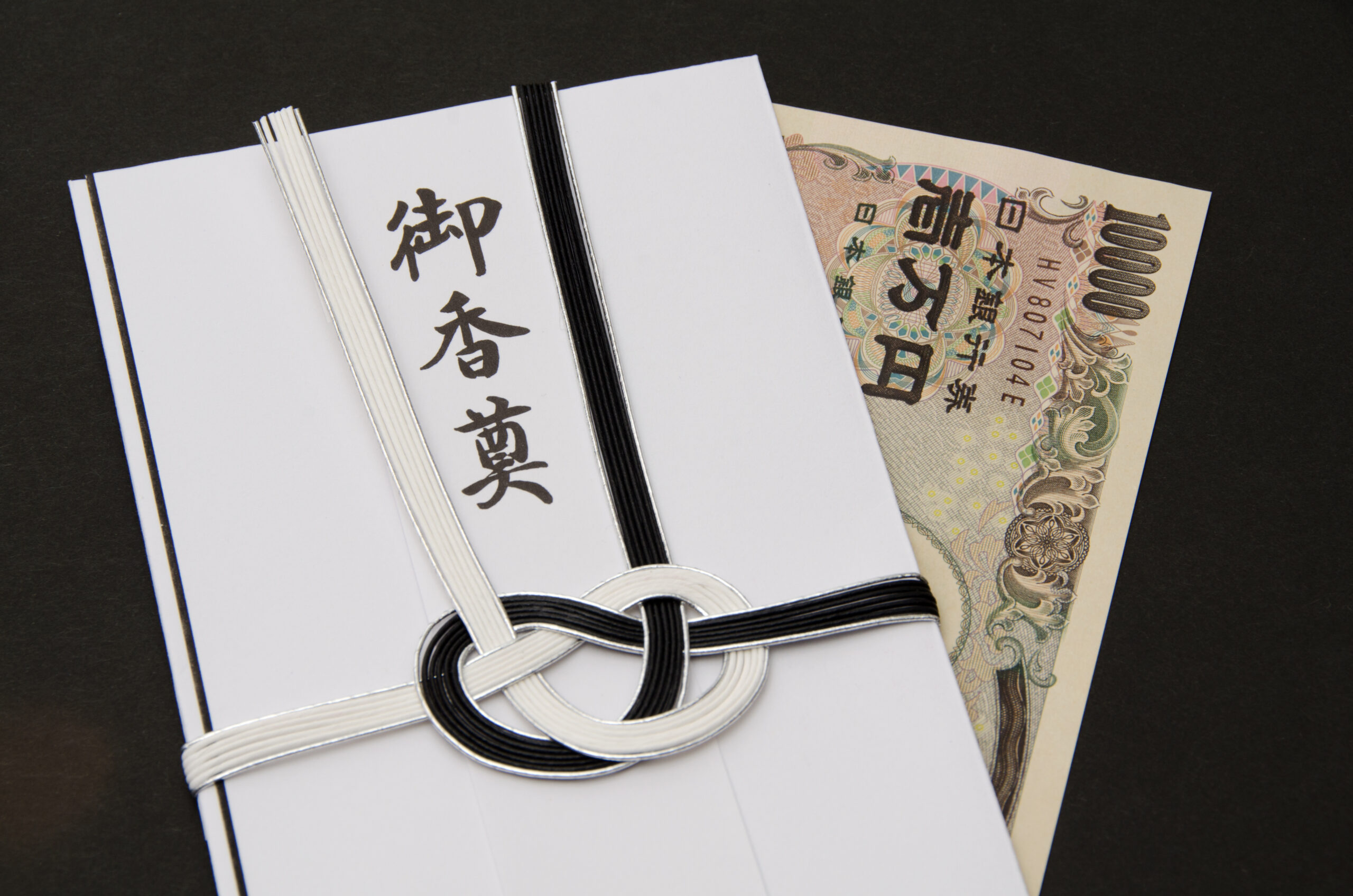お墓参りは、故人を偲び、ご先祖様に感謝の気持ちを伝える大切な時間です。
その際に欠かせないものの一つが、お供えする花ではないでしょうか。
色とりどりの花は、お墓を華やかに彩るだけでなく、私たちの心を穏やかにしてくれます。
しかし、いざお墓に供える花を選ぼうと思うと、「どんな花が良いのだろう」「避けるべき花はあるのかな」と、葬儀のお墓に供える花選びのマナーについて悩む方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、お墓参りにふさわしい花の選び方から、供え方のマナー、そして知っておきたい注意点までを、初心者の方にも分かりやすく丁寧にご紹介します。
故人を想う気持ちを込めて、心温まるお墓参りの準備をしましょう。
お墓参りで花を供える大切な意味と基本マナー
お墓参りの際に花を供える行為は、単に墓前を美しく飾るためだけではありません。
そこには、古くから伝わる深い意味合いが込められています。
花は、美しい姿と香りで私たちの心を癒し、穏やかな気持ちにさせてくれます。
お墓に花を供えることは、まず故人の霊を慰め、安らかに眠ってほしいという願いを込める行為です。
また、仏教では、花は仏様の慈悲の心を象徴すると考えられており、仏様や故人への感謝の気持ちを表すものとされています。
さらに、お墓という静かで少し寂しさを感じる場所に、生命力あふれる花を供えることで、生と死をつなぎ、故人が今も私たちの心の中で生き続けていることを実感する機会にもなります。
花は枯れてしまうものですが、その枯れる過程もまた、命の循環や無常観を表していると捉えることもできます。
このように、お墓に花を供えるという行為には、故人への供養、感謝の表現、そして生と死への向き合い方といった、様々な意味が込められているのです。
だからこそ、どのような花を選ぶか、どのように供えるかといったマナーも大切にされてきました。
マナーを守ることは、故人やご先祖様への敬意を示すだけでなく、同じお墓を利用する他の方々への配慮にもつながります。
これからご紹介する基本マナーを知っておくことで、より心を込めたお墓参りができるようになるでしょう。
なぜお墓に花を供える習慣があるのか
お墓に花を供える習慣は、古くから日本だけでなく世界中の様々な文化で見られます。
その起源には諸説ありますが、仏教においては、花は「智慧(ちえ)」や「慈悲(じひ)」を象徴するものとされ、仏様へのお供えとして非常に重要視されてきました。
お釈迦様が説法をする際にも、天から花が降ってきたという逸話があるほどです。
また、花は生きとし生けるものの命の尊さや、やがて枯れることによる無常観を表すとも言われています。
このため、お墓に花を供えることは、故人の魂を慰めると同時に、私たち自身が命のはかなさや尊さを感じ、日々の生活を大切にするための教えとして受け継がれてきました。
さらに、花のもつ清らかさや美しさが、お墓という神聖な場所を浄化し、邪気を払うと考えられていた側面もあります。
昔は、今のように手軽に線香やろうそくが手に入らなかった時代もあり、香り高い花や葉を供えることで、その場を清める役割も担っていたようです。
現代では、お墓参りにおける花は、故人の好きだった花を供えることで、故人への愛情や思い出を形にするという意味合いも強くなっています。
単なる習慣としてではなく、こうした様々な意味が込められていることを理解することで、お墓に供える花を選ぶ行為そのものが、より一層心温まるものになるのではないでしょうか。
特に、故人が生前大切にしていた花や、思い出の花を選ぶことは、何よりの供養になると言えます。
それは、単に形式的なマナーを守るだけでなく、故人との絆を感じるための大切な時間となるからです。
お墓に供える花の色選びのポイント
お墓に供える花の色選びには、いくつかのポイントがあります。
基本的には、故人を追悼する意味合いから、落ち着いた色合いの花を選ぶことが一般的です。
白、黄色、紫などがよく選ばれます。
特に白は清らかさや故人への哀悼の意を表す色として、仏事全般で用いられます。
黄色や紫は、気品があり、仏様の世界を連想させる色として好まれます。
これらの色を組み合わせた花束は、お墓参りの供花として最も定番と言えるでしょう。
しかし、最近では、故人の好きだった色や、明るい色の花を供えることも増えてきています。
これは、故人を悼む気持ちだけでなく、故人の魂が安らかであること、そして遺族が前向きに生きていくことを願う気持ちが反映されていると考えられます。
例えば、故人が明るい性格だった場合や、華やかな色が大好きだった場合は、ピンクやオレンジ、水色といった優しい色合いの花を少量加えることも問題ありません。
ただし、あまりにも派手すぎる色や、原色ばかりの花束は、お墓の厳粛な雰囲気にそぐわないと考える人もいるため、全体のバランスを考慮することが大切です。
また、地域や宗派によっては、特定の色にこだわりがある場合もあります。
迷った際は、ご家族や親戚に相談してみるのも良いでしょう。
一般的には、白を基調としつつ、黄色、紫、または故人の好きだった色をアクセントに加えるのが、失礼にあたらず、かつ故人を偲ぶ気持ちも表現できる選び方と言えます。
大切なのは、形式にとらわれすぎず、故人への想いを込めて色を選ぶことです。
例えば、お孫さんが描いた絵の色合いに合わせて花を選んだり、故人が生前育てていた花の色を参考にしたりと、パーソナルな要素を取り入れることで、より心に残るお供えになるでしょう。
供える花束の形や本数の考え方
お墓に供える花束の形や本数についても、伝統的な考え方があります。
一般的には、左右一対になるように同じ形の花束を2つ用意します。
これは、仏壇に供える仏花と同様に、バランスを重視し、整った状態でお供えするためです。
花束の形は、墓石の横にある花立てに挿しやすいように、茎がある程度まとまっているものが良いでしょう。
長さは、花立ての高さに合わせて調整できるように、少し長めに準備しておくと安心です。
お墓参りでは、風が強い日もあるため、あまり背が高すぎると倒れやすいことも考慮が必要です。
本数については、仏花としては奇数が良いとされることが多いです。
これは、割り切れない数である奇数が縁起が良いと考えられたり、陰陽五行説に基づいたりする理由からです。
具体的には、3本、5本、7本といった本数が一般的です。
ただし、最近では本数にそれほどこだわらない方も増えており、花の種類やボリュームに合わせて見栄えの良い本数を選ぶこともあります。
例えば、大きな菊を一輪だけ供える、といった地域や宗派独自の風習がある場合もありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
また、花束にする際は、茎の下の方にある葉っぱを取り除いておくと、花立ての水が汚れにくく、花が長持ちしやすくなります。
特に夏場は水が腐りやすいため、この一手間が非常に重要です。
花束を組む際は、中心に背の高い花を配置し、周りに小ぶりな花や葉ものを配すると、バランスの良い美しい仕上がりになります。
左右対称に供えるため、全く同じ花材と本数で2つの花束を準備するのが基本です。
ただし、最近の霊園では花立てが一つしかない場合や、区画が狭い場合もありますので、その際は一つにまとめて供えることもあります。
状況に合わせて臨機応変に対応することも大切です。
お墓にふさわしい花と避けるべき花の種類
お墓に供える花には、一般的にふさわしいとされる種類と、避けた方が良いとされる種類があります。
これは、マナーとしてだけでなく、お墓という場所の特性や、仏教的な考え方に基づいていることが多いです。
まず、お墓にふさわしい花としては、日持ちが良く、比較的香りが控えめで、トゲがないものが挙げられます。
代表的なのは、菊、ユリ、カーネーション、リンドウなどです。
これらの花は、古くから仏花として親しまれており、お墓参りの定番と言えるでしょう。
菊は、その高貴な姿と日持ちの良さから、仏花の代表格とされています。
ユリは、清らかな香りと美しい姿が好まれますが、花粉が墓石を汚す可能性があるため、事前に花粉を取り除いておく配慮が必要です。
カーネーションは、色持ちが良く丈夫なため、特に夏場のお墓参りにも適しています。
リンドウは、落ち着いた紫の色合いが仏事にふさわしいとされます。
これらの定番の花を中心に、季節の花や、故人の好きだった花を組み合わせることで、より心を込めた供花になります。
例えば、春にはアイリスやフリージア、夏にはグラジオラスやトルコキキョウ、秋にはケイトウやコスモス、冬にはストックやスイートピーなどを加えるのも良いでしょう。
ただし、季節の花は日持ちがあまりしないものもあるため、その点は考慮が必要です。
お墓に供える花は、故人を偲ぶ気持ちを表すものなので、見た目の美しさだけでなく、その花が持つ意味合いや、お墓という場所に合った性質を持つかどうかも大切です。
次に、避けるべき花について詳しく見ていきましょう。
お墓の供花として定番とされる花
お墓の供花として古くから親しまれ、定番とされている花には、いくつかの種類があります。
その中でも特に代表的なのは「菊」です。
菊は、日本の秋を代表する花であり、皇室の紋章にも使われるほど高貴な花とされています。
また、日持ちが非常に良いこと、一年を通して手に入りやすいこと、そして香りが控えめであることから、仏花の代表格となりました。
特に、輪菊(りんぎく)と呼ばれる大輪の菊は、お盆やお彼岸、法事などの重要な時期によく用いられます。
次に定番なのが「ユリ」です。
ユリは、その清らかで美しい姿と、上品な香りが特徴です。
白や淡い色合いのユリは、お墓の厳かな雰囲気に良く合います。
ただし、ユリの花粉は墓石や衣服に付くと落ちにくいため、供える前に雄しべを取り除くのがマナーとされています。
この一手間をかけることで、気持ちよくお供えすることができます。
また、「カーネーション」も定番の一つです。
特にピンクや白のカーネーションは、母の日のイメージが強いかもしれませんが、仏花としても広く使われています。
花持ちが良く、比較的安価で手に入りやすい点が魅力です。
そして、「リンドウ」も仏花としてよく知られています。
リンドウの濃い紫色は、古くから高貴な色とされており、仏様への供養の色としてふさわしいと考えられています。
これらの定番の花を中心に、季節ごとの花や、故人の好きだった花を加えて花束を作ることが多いです。
例えば、故人がバラが好きだった場合でも、トゲのない品種を選んだり、トゲを丁寧に取り除いたりすれば、お墓に供えることも可能です。
定番の花は、日持ちや香りの面でお墓に適しているため、迷ったときはこれらの花を選ぶのが安心です。
花屋さんで「お墓参り用の花」と伝えると、これらの定番の花を中心にアレンジしてくれることが多いでしょう。
お墓には不向きとされる花とその理由
お墓に供える花として、一般的に避けた方が良いとされる花には、いくつかの特徴があります。
まず、トゲのある花は避けるのがマナーです。
代表的なのはバラやアザミなどです。
これは、仏教において「殺生」を連想させることや、お墓参りをする際に手を傷つける可能性があるためです。
故人への敬意や、お墓という神聖な場所への配慮として、トゲのある花は避けるべきとされています。
ただし、故人がバラをこよなく愛していたなどの特別な理由がある場合は、トゲを丁寧に取り除けば供えることもあります。
次に、香りの強すぎる花も避けた方が良いとされる場合があります。
ユリやキンモクセイ、カサブランカなどが該当します。
香りが強すぎると、他のお墓参りの方の迷惑になったり、虫を寄せ付けやすくなったりする可能性があるためです。
特に夏場は香りが広がりやすく、虫も増えるため注意が必要です。
また、毒のある花や、毒を持つ可能性のある花も避けるべきです。
彼岸花(曼珠沙華)やスズランなどがこれにあたります。
これは、誤って口にしたり、小さなお子さんが触れたりする危険性があるためです。
お墓は公共の場でもあるため、安全への配慮が求められます。
さらに、ツル性の花や、すぐに散ってしまう花もあまりお墓向きではありません。
ツル性の花は、墓石に絡みついてしまう可能性があり、手入れが大変になることがあります。
すぐに散ってしまう花は、せっかく供えてもすぐに枯れてしまい、見た目が悪くなってしまうためです。
例えば、チューリップやサクラなどは、咲いている期間が短く、散りやすいため、お墓にはあまり適しません。
また、慶事を連想させるような華やかすぎる花(例:結婚式でよく使われるような色合いやアレンジ)も、追悼の場であるお墓にはふさわしくないとされることが多いです。
これらの点を踏まえ、お墓という場所の性質や、他の方への配慮を考えて花を選ぶことが大切です。
造花やプリザーブドフラワーの扱いについて
お墓に供える花といえば、生花が一般的ですが、近年では造花やプリザーブドフラワーを供える方も増えています。
これらを生花と同様に扱って良いのか、迷う方もいらっしゃるかもしれません。
まず、造花についてですが、造花をお墓に供えること自体は、必ずしもマナー違反ではありません。
特に、頻繁にお墓参りに行けない場合や、夏場の暑い時期など、生花がすぐに傷んでしまう状況では、造花の方が管理が楽で、お墓を常に綺麗に保つことができるというメリットがあります。
最近の造花は品質が高く、見た目が生花と見分けがつかないほど美しいものも増えています。
ただし、造花を供える際に注意したいのは、あまりにも安っぽいものや、色あせたり汚れたりしているものを放置しないことです。
造花であっても、定期的にお手入れをし、古くなったら交換することが、故人やご先祖様への敬意を示す上で大切です。
また、霊園によっては、管理規約で造花の持ち込みを禁止している場合もありますので、事前に確認しておくのが安心です。
次に、プリザーブドフラワーについてです。
プリザーブドフラワーは、生花を特殊な加工によって長期間保存できるようにしたもので、生花のような自然な風合いと色合いを保ちながら、水やりなどの手入れが不要という特徴があります。
造花よりも生花に近い雰囲気があり、枯れないため美しい状態を長く保つことができます。
プリザーブドフラワーも、造花と同様に、頻繁にお墓参りに行けない方にとっては有効な選択肢となり得ます。
ただし、屋外で使用することを想定していないものが多いため、雨や直射日光に弱い場合があり、屋外のお墓で長期間飾るには耐久性に問題がある可能性もあります。
また、コストが生花よりも高くなる傾向があります。
生花、造花、プリザーブドフラワー、それぞれにメリット・デメリットがあります。
故人やご遺族の考え方、お墓参りの頻度、お墓の環境などを考慮して、最も適したものを選ぶのが良いでしょう。
最も大切なのは、どのような形であれ、故人を想い、心を込めてお供えすることです。
お墓の供花に関する実践的な準備と注意点
お墓参りに行く際に、供花をどのように準備し、お墓でどのように扱うかを知っておくことは、スムーズで心穏やかなお墓参りのために重要です。
まず、花束の準備ですが、事前に花屋さんで購入するのが一般的です。
花屋さんで「お墓参り用の花束」と伝えると、仏花として適した花材を選んで、左右一対になるように組んでくれます。
この際、花立ての大きさを伝えたり、故人の好きだった花や色などの希望を伝えたりすると、よりパーソナルな花束を用意してもらえます。
購入後は、持ち運び中に花が傷まないように注意が必要です。
特に夏場は、暑さで花がしおれてしまう可能性があるため、保冷剤と一緒に持ち運んだり、水を含ませたキッチンペーパーなどで茎の切り口を包んだりする工夫をすると良いでしょう。
車で移動する場合は、エアコンの効いた車内に置くのが理想的です。
電車やバスの場合は、他の乗客の迷惑にならないように、花の向きや香りに配慮することも大切です。
お墓に着いたら、まずはお墓周りの掃除を済ませ、それから花を供えるのが一般的な流れです。
花立ての古い花を取り除き、綺麗に洗ってから新しい花を活けます。
花を活ける際は、花立ての深さに合わせて茎の長さを調整します。
ハサミやナイフが必要になる場合があるので、お墓参りセットに加えておくと便利です。
水は、霊園にある水道を利用するか、持参した水を使います。
花立てに新鮮な水をたっぷり入れ、花を挿します。
左右一対になるように、バランス良く飾りましょう。
供えた花は、常に綺麗にしておくことが故人への供養となるため、定期的にお墓参りに行き、水換えや枯れた花の処理を行うことが理想です。
しかし、遠方に住んでいるなどで頻繁に行けない場合は、霊園の管理事務所に相談したり、造花を利用したりすることも検討できます。
お墓へ持っていく花の準備と持ち運びのコツ
お墓参りに行く前に、花を準備する段階から気を配ることが大切です。
まず、花屋さんで花束を購入する際は、できるだけ新鮮な花を選んでもらいましょう。
茎の切り口が新しく、葉っぱがピンとしているものが新鮮な証拠です。
花屋さんで「お墓参り用」と伝える際に、いつお墓参りに行くかを伝えておくと、それに合わせて日持ちの良い花を選んでくれたり、蕾の多いものを選んでくれたりします。
花束を受け取ったら、持ち運び中に花が傷まないように工夫が必要です。
特に、車での移動時間が長い場合や、公共交通機関を利用する場合は、花の保護が重要になります。
夏場は、車内の温度が高くなりやすく、花がすぐにしおれてしまいます。
そのため、持ち運び用のバケツに少量の水を入れて花を立てて運んだり、保冷バッグに保冷剤と一緒に入れたりするのがおすすめです。
茎の切り口を濡らしたキッチンペーパーで包み、ビニール袋などで覆うだけでも、乾燥を防ぐ効果があります。
冬場は、凍結に注意が必要です。
寒すぎると花が傷んでしまうこともあるので、暖かい場所で保管し、移動中も冷たい風に長時間当てないように気をつけましょう。
また、花束を包むラッピングは、お墓に供える際に外すのが一般的です。
お墓に着いてからスムーズに作業できるように、簡単に解けるラッピングにしてもらうか、自宅で外しておくと良いでしょう。
持ち運びの際は、花が下向きにならないように、また他の荷物とぶつかって花びらが傷つかないように注意しましょう。
電車やバスの中では、周りの方への配慮も忘れずに。
大きな花束の場合は、抱えるように持つか、専用のバッグに入れるなどして、邪魔にならないように気をつけましょう。
これらのちょっとした工夫で、お墓に着いた時に、美しい状態の花を故人に供えることができます。
お墓での供え方と水換えなどの手入れ
お墓に到着したら、まずは墓石やその周囲をきれいに掃除します。
古い花や枯葉、雑草などを取り除き、墓石を水洗いして拭き上げましょう。
掃除が終わったら、いよいよ花を供えます。
まず、花立てに溜まった古い水やゴミを捨て、きれいに洗い流します。
花立ては、長期間水を入れっぱなしにしているとヌメりや苔が発生しやすいので、ブラシなどを使って丁寧に洗うことが大切です。
花立てがきれいになったら、新鮮な水を八分目ほど入れます。
水が少ないと花がすぐに枯れてしまうため、たっぷり入れるのがポイントです。
次に、持ってきた花束の茎の長さを調整します。
花立てに挿した時に、花の先端が墓石の竿石(一番上の石)の高さと同じくらいか、やや低めになるのがバランスが良いとされています。
茎が長すぎると風で倒れやすくなりますし、短すぎると花が隠れてしまいます。
ハサミで茎を斜めに切ると、水を吸い上げやすくなり、花が長持ちします。
左右一対の花立てがある場合は、同じ形になるように花を活けましょう。
花束をそのまま活けるのではなく、花立ての大きさに合わせて花をばらして活ける方が、水が全体に行き渡りやすく、花が長持ちすることもあります。
供えた後は、定期的に水換えや枯れた花の処理を行うことが、お墓を美しく保ち、故人への敬意を示す上で非常に重要です。
特に夏場は水が腐りやすく、悪臭の原因にもなるため、こまめな水換えが必要です。
もし頻繁にお墓参りに行けない場合は、水が蒸発しにくいように花立てに蓋をする、保水ジェルを使う、といった対策も有効です。
これらの手入れを怠ると、かえってお墓を汚してしまうことになるため、供えた後の管理も責任を持って行うことが大切です。
お墓参りの後に残った花の適切な扱い方
お墓参りが終わった後、供えた花をどうするかは、地域や霊園、ご家庭の考え方によって異なります。
一般的には、お墓参りの際に供えた花は、そのまま置いて帰るのが基本です。
これは、故人に供えたものを持ち帰るのは失礼にあたるという考え方や、次に訪れる方のために墓前を華やかに保っておくという意味合いがあります。
特に、お盆やお彼岸、法事など、多くの人がお墓参りに来る時期は、供花がたくさん並んでお墓全体が華やかになるため、そのまま置いて帰るのが一般的です。
しかし、最近では環境への配慮や、次にいつお墓参りに来られるか分からないといった理由から、供えた花を持ち帰る方も増えています。
特に夏場は、花がすぐに枯れてしまい、かえってお墓を汚してしまう可能性があるため、持ち帰って処分する方が良いと考える人もいます。
持ち帰る場合は、そのままゴミとして処分しても問題ありませんが、故人への感謝の気持ちを込めて、新聞紙に包んでから捨てるなど、丁寧な扱いを心がける方もいらっしゃいます。
また、自宅に持ち帰って仏壇に供えたり、庭に植えたり(球根や根のある花の場合)する方もいます。
ただし、霊園によっては、供えた花を持ち帰ることを推奨している場合や、逆に持ち帰りを禁止している場合もあります。
霊園の管理規約を確認するか、管理事務所に問い合わせてみるのが最も確実です。
もし持ち帰りを推奨されている場合は、次に訪れる方のために花立てを空けておくという意味合いもあります。
どちらの場合でも、大切なのは故人を想う気持ちです。
そのまま置いて帰るにしても、持ち帰るにしても、故人への感謝の気持ちを持って適切に扱うことが重要です。
迷った場合は、ご家族や親戚と相談して、皆で納得できる方法を選ぶのが良いでしょう。
お墓に残して帰る場合は、風で飛ばされたり、他の区画に迷惑をかけたりしないように、花立てにしっかりと挿しておくことが大切です。
まとめ
お墓に供える花選びは、単に墓前を飾るだけでなく、故人を偲び、ご先祖様への感謝の気持ちを伝える大切な行為です。
この記事では、「葬儀のお墓に供