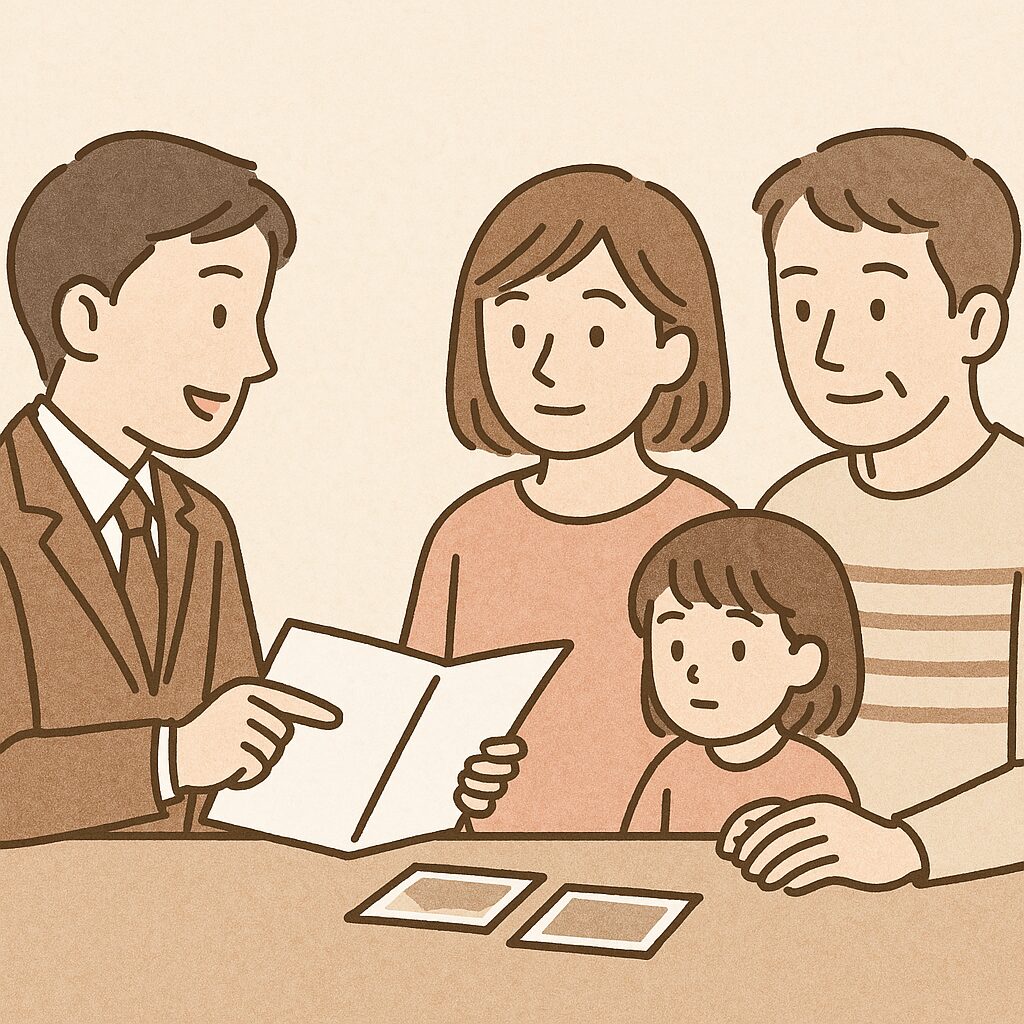神道における葬儀やお墓について、あなたはどのようなイメージをお持ちでしょうか?仏式とは異なる儀式や考え方があると知っていても、具体的にどう違うのか、どのような流れで進むのか、そしてお墓やその後の供養はどうするのか、分からないことが多いかもしれません。
この記事では、神道ならではの死生観に基づいた葬儀(神葬祭)の考え方から、具体的な儀式、費用、マナー、そしてお墓や死後の祭祀に至るまで、「神道における葬儀とお墓について」知りたいことすべてを、分かりやすく丁寧にご説明します。
神道のご葬儀やお墓を控えている方、あるいは神道について深く理解したい方にとって、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
神道における葬儀の基本的な考え方と流れ
神道では、人間は亡くなるとその御霊(みたま)が家の守護神となり、子孫を見守ると考えられています。
このため、神道の葬儀は故人の御霊を家の守護神として祀り、子孫の繁栄を願うための重要な儀式と位置づけられます。
仏教の「成仏」とは異なり、神道では「神となる」という考え方が根底にあります。
この独特な死生観が、神葬祭と呼ばれる葬儀の儀式や流れに大きく影響を与えています。
神葬祭は、故人が現世から幽世(かくりよ)と呼ばれる神様の世界へ遷り変わるための一連の儀礼であり、遺族にとっては故人の御霊を慰め、今後の安寧を祈る大切な時間です。
仏式では通夜、葬儀・告別式、初七日法要などが行われますが、神道では通夜祭、葬場祭、遷霊祭、帰家祭など、独自の名称と意味を持つ儀式が執り行われます。
これらの儀式を通じて、故人の御霊を清め、霊璽(れいじ:仏式の位牌にあたるもの)に移し、祖霊舎に祀る準備を進めていきます。
神葬祭は、故人の魂を家の中に留め、家族と共に永く祀っていくための始まりの儀式と言えるでしょう。
仏式とは異なる神道独自の儀礼や考え方を理解することで、神葬祭に対する向き合い方も変わってくるはずです。
神道が考える「死」とは?仏式との違い
神道における「死」は、仏教のように「この世からあの世へ旅立ち、悟りを開いて成仏する」という考え方とは根本的に異なります。
神道では、人間の魂は肉体から離れても消滅するのではなく、「幽世(かくりよ)」という神様の世界へ遷り変わり、家の守護神として子孫を見守ると考えられています。
このため、神道の葬儀である神葬祭は、故人の御霊を清め、家の守護神としてお迎えするための儀式という側面が強いのです。
仏教では、故人の魂は四十九日の旅を経て極楽浄土へ向かうとされ、遺族は故人の成仏を願って供養を行います。
一方、神道では、故人の御霊は家の祖霊舎(それいしゃ)に祀られ、日常的に家族と共に過ごすと捉えられます。
故人が「神」となるという考え方は、神道の根幹にある多神教や祖霊信仰に基づいています。
自然や祖先を敬い、すべてのものに神が宿ると考える神道では、個人の死もまた、家系の連続性の中での一つの節目であり、故人が祖霊の一員として家を守る存在に昇華すると捉えられるのです。
このため、神葬祭では故人の神格化を促す儀式が中心となり、遺族は故人の御霊を大切に祀り続けることが重要視されます。
仏式との大きな違いは、故人の魂が家から離れていくのではなく、むしろ家の中へと迎え入れられるという点にあると言えるでしょう。
この神道独自の死生観を理解することが、神葬祭やお墓、その後の祭祀を理解する上で非常に重要になります。
神葬祭(しんそうさい)の主な儀式と意味
神葬祭は、仏式でいう通夜、葬儀・告別式にあたる一連の儀式を指します。
主な儀式としては、まず「帰幽奉告(きゆうほうこく)」があり、これは家族が亡くなったことを神棚や祖霊舎に奉告する儀式です。
その後、故人の枕元に仮の祭壇を設け、「枕直しの儀(まくらなおしのぎ)」を行います。
そして、仏式の通夜にあたる「通夜祭(つやさい)」が執り行われます。
通夜祭では、神職が故人の御霊を慰めるための祝詞(のりと)を奏上し、遷霊祭(せんれいさい)の準備を行います。
遷霊祭は、故人の御霊を遺体から霊璽(れいじ)へ遷し替える儀式であり、神葬祭の中で最も重要かつ神秘的な儀式の一つとされています。
この儀式を通じて、故人の御霊は霊璽に宿り、家の守護神となる準備が整います。
続いて、仏式の葬儀・告別式にあたる「葬場祭(そうじょうさい)」が斎場などで執り行われます。
葬場祭では、神職による祭詞奏上、弔辞奉呈、弔電奉読などが行われ、参列者による玉串奉奠(たまぐしほうてん)が行われます。
玉串奉奠は、仏式の焼香にあたる儀式で、故人への弔意を表し、御霊の平安を祈るために玉串を捧げます。
これらの主要な儀式以外にも、火葬前に執り行われる「火葬祭(かそうさい)」や、火葬後に自宅に戻った際に行われる「帰家祭(きかさい)」などがあります。
帰家祭では、無事に葬儀を終えたことを神棚や祖霊舎に奉告し、遺骨や霊璽を仮の祭壇に安置します。
神葬祭の各儀式には、故人の御霊を清め、慰め、家の守護神として迎えるための深い意味が込められています。
葬儀の流れと特徴:仏式との比較
神葬祭の流れは、仏式葬儀と似ている部分もありますが、いくつか大きな違いがあります。
一般的には、まず「帰幽奉告」から始まり、「枕直しの儀」を経て、仏式の通夜にあたる「通夜祭」が執り行われます。
通夜祭の後には、故人の御霊を霊璽に移す重要な儀式である「遷霊祭」が行われるのが特徴です。
遷霊祭は夜に行われることが多く、この儀式によって故人の御霊は霊璽に宿り、家の守護神となる準備が整います。
翌日には、仏式の葬儀・告別式にあたる「葬場祭」が斎場などで執り行われます。
葬場祭では、神職による祭詞奏上や玉串奉奠が行われます。
玉串奉奠は、榊の枝に紙垂(しで)をつけた玉串を捧げる儀式で、仏式の焼香のように故人への弔意を表します。
その後、出棺となり、火葬場へ向かう前に「火葬祭」が行われ、火葬後に自宅に戻って「帰家祭」が行われます。
帰家祭では、仮の祭壇に遺骨と霊璽を安置します。
仏式との最大の違いは、読経や戒名がなく、神職が祝詞を奏上し、故人の生前の功績を称え、神としての位階にあたる諡(おくりな)を贈る点です。
また、焼香の代わりに玉串奉奠を行うこと、そして仏壇ではなく祖霊舎に故人の霊璽を祀ることが挙げられます。
仏式では故人の成仏を願いますが、神道では故人が家の守護神となることを願うため、儀式の意味合いが異なります。
神葬祭は、仏教の教えではなく、神道古来の考え方に基づいているため、儀式や作法に違いが見られます。
これらの違いを理解することで、神葬祭への参列や準備をスムーズに進めることができるでしょう。
神道葬儀の費用とマナー、参列の注意点
神道における葬儀、すなわち神葬祭にかかる費用は、仏式葬儀と同様に、葬儀の規模や内容、参列者の人数などによって大きく変動します。
しかし、仏式葬儀にはない独特の費用項目や、神道ならではのマナーが存在します。
費用面では、斎場使用料、祭壇料、棺、骨壺、人件費、飲食接待費などに加えて、神職への謝礼である「御祭祀料(おさいしりょう)」が必要となります。
この御祭祀料は、仏式の御布施にあたるもので、神職の階級や葬儀の内容によって金額は異なりますが、一般的には仏式の御布施と同等か、やや高めになる傾向があるとも言われます。
また、祭壇や装飾も、仏式とは異なり、榊や生花、神饌(しんせん:神様へのお供え物)などが用いられるため、その準備にかかる費用も考慮する必要があります。
マナーに関しては、服装は仏式と同様に喪服が一般的ですが、数珠は使用しません。
香典にあたるものは「玉串料(たまぐしりょう)」または「御榊料(おさかきりょう)」と呼び、不祝儀袋の表書きも「御玉串料」や「御榊料」と記載します。
蓮の絵が描かれた不祝儀袋は仏式用なので避けるのがマナーです。
参列の際には、玉串奉奠の作法を知っておくことが重要です。
玉串を神職から受け取り、一礼して祭壇に進み、玉串を時計回りに回して根元を手前にして供え、二礼二拍手一礼(しのび手)の作法で拝礼します。
この「しのび手」は音を立てない拍手であり、弔いの意を表す神道独自の作法です。
神葬祭にかかる費用とその内訳
神葬祭にかかる費用は、仏式葬儀と同様に、葬儀の規模や形式(家族葬、一般葬など)、参列者の数、斎場の場所や設備などによって大きく異なります。
一般的な内訳としては、主に以下の項目が挙げられます。
まず、斎場使用料や火葬場使用料があります。
次に、祭壇の設営費用です。
神道の祭壇は、仏式とは異なり、白木を基調とし、榊や生花、神饌などが供えられます。
この祭壇の規模や装飾によって費用は変動します。
棺や骨壺、遺影写真、寝台車や霊柩車などの費用も含まれます。
さらに、葬儀を執り行う神職への謝礼である「御祭祀料(おさいしりょう)」が必要です。
これは仏式の御布施にあたるもので、神職の階級や葬儀の内容、所要時間などによって金額が決まりますが、明確な料金体系がない場合が多く、事前に神職や葬儀社に相談することが大切です。
一般的に、御祭祀料の目安は仏式の御布施と同程度か、やや高めになることもあると言われています。
その他、会葬御礼品や飲食接待費(通夜振る舞いや精進落としにあたるもの)なども費用に含まれます。
神葬祭特有の費用として、神饌の準備にかかる費用や、玉串奉奠に使う榊の費用などがあります。
これらの費用は、葬儀社に見積もりを依頼する際に詳細を確認し、内容をよく理解しておくことが重要です。
事前に複数の葬儀社から見積もりを取り、比較検討することで、納得のいく費用で神葬祭を執り行うことができるでしょう。
予算に合わせて、必要なサービスとそうでないサービスを見極めることも大切です。
参列者の服装と香典(玉串料)のマナー
神葬祭に参列する際の服装は、基本的に仏式葬儀と同様に喪服が一般的です。
男性はブラックスーツに白いワイシャツ、黒いネクタイと靴下、黒い靴を着用します。
女性はブラックフォーマルと呼ばれる黒いワンピースやアンサンブル、スーツなどを着用し、ストッキングや靴も黒色を選びます。
アクセサリーは結婚指輪以外は控えめにし、華美なものは避けます。
学生の場合は制服、子供の場合は地味な色の服装であれば問題ありません。
神葬祭では、仏式葬儀で一般的に使用される数珠は必要ありませんので持参しないようにしましょう。
また、仏式の葬儀でよく見かける袈裟や輪袈裟なども神道では使用しません。
香典にあたるものは「玉串料(たまぐしりょう)」または「御榊料(おさかきりょう)」と呼びます。
不祝儀袋の表書きは「御玉串料」「御榊料」または「御霊前」と記載します。
蓮の絵が描かれた不祝儀袋は仏式用なので、神道では使用しません。
水引の色は黒白または双銀、結び切りを選びます。
金額の目安は、故人との関係性や自身の年齢によって異なりますが、一般的には仏式の香典と同程度と考えて良いでしょう。
ただし、地域や家によっては慣習が異なる場合もありますので、心配な場合は事前に親族などに確認してみるのが安心です。
玉串料は、通夜祭または葬場祭の受付で、袱紗(ふくさ)から取り出して渡すのが丁寧なマナーです。
不祝儀袋の向きにも注意し、相手から見て表書きが正しく読めるように渡しましょう。
神葬祭に参列する際の独特な作法
神葬祭に参列する際には、仏式葬儀とは異なる神道独自の作法がいくつかあります。
最も特徴的なのは、「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」と呼ばれる儀式です。
これは仏式の焼香にあたるもので、故人への弔意を表し、御霊の平安を祈るために玉串(榊の枝に紙垂をつけたもの)を祭壇に捧げます。
玉串奉奠の手順は、まず神職または案内の人に従って祭壇に進み、神職から玉串を受け取ります。
玉串は右手で枝元を上から持ち、左手で葉先を下から支えるように持ちます。
祭壇の前で一礼し、玉串を時計回りに回して、根元を祭壇側(手前)に向けて捧げます。
玉串を供えたら、二礼二拍手一礼の作法で拝礼します。
ただし、この時の拍手は「しのび手」と言い、音を立てずに手を合わせるのが神道独自の作法です。
これは、弔いの場において喜びの音である拍手を控えるという意味が込められています。
拝礼が終わったら、一歩下がって再度一礼し、席に戻ります。
もう一つの注意点は、手を清める「手水(てみず)」の作法です。
斎場の入り口などに手水舎が設けられている場合があり、参列者はここで手と口を清めてから式場に入ります。
まず柄杓(ひしゃく)で水を汲み、左手、右手の順に清め、次に左手に水を受けて口をすすぎ、最後に柄杓を立てて柄の部分を清めて元の位置に戻します。
これは神社に参拝する際の手水と同じ作法です。
これらの独特な作法を知っておくことで、自信を持って神葬祭に参列することができるでしょう。
神道におけるお墓と死後の祭祀
神道におけるお墓は、故人の御霊が宿る霊璽(れいじ)と共に、家の守護神として家族を見守るための大切な場所です。
仏式のお墓と同様に、遺骨を納めるためのものではありますが、その形状や墓石に刻む文字など、神道ならではの特徴があります。
神道のお墓は「奥都城(おくつき)」または「奥津城」と呼ばれ、仏式の墓石に見られるような仏様の名前や梵字、戒名などは刻まれません。
代わりに、故人の生前の名前や諡(おくりな)、あるいは「〇〇家之奥都城」といった文字が刻まれるのが一般的です。
墓石の形状も、仏式で一般的な和型墓石とは異なり、角柱型や独特な神道型のものが見られます。
また、お墓の敷地内には、鳥居や玉垣、燈籠などが設けられることもあり、神聖な空間として位置づけられます。
納骨に関しては、仏式と同様に火葬後に遺骨をお墓に納めますが、神道では故人の御霊は霊璽に宿ると考えるため、お墓はあくまで依代(よりしろ)の一つとして捉えられる側面もあります。
死後の祭祀は、仏式の法要にあたる「年忌祭(ねんきさい)」が中心となります。
年忌祭は、故人の没後一年目の「一年祭」から始まり、三年祭、五年祭、十年祭、五十年祭など、特定の年に執り行われます。
これらの祭祀を通じて、故人の御霊を慰め、感謝の気持ちを捧げ、家系の繁栄を祈ります。
また、自宅に祀る祖霊舎(それいしゃ)は、故人の御霊が宿る霊璽を安置する場所であり、日常的に家族が故人に手を合わせるための大切な空間です。
神道におけるお墓と死後の祭祀は、故人の御霊を大切に祀り、家系の continuity を守り継いでいくという神道独自の考え方に基づいています。
神道のお墓の特徴と仏式との違い
神道のお墓は「奥都城(おくつき)」と呼ばれ、仏式のお墓とはいくつかの点で異なります。
最も分かりやすい違いは、墓石に刻む文字です。
仏式では「南無阿弥陀仏」や「南無妙法蓮華経」といった仏様の名前や経文、あるいは戒名が刻まれるのが一般的ですが、神道のお墓にはこれらの文字は一切刻まれません。
代わりに、故人の生前の名前や諡(おくりな)、あるいは「〇〇家之奥都城」といった文字が刻まれます。
これは、神道が仏教とは異なる信仰に基づいているためであり、故人を仏様としてではなく、家の守護神として祀るという考え方が反映されています。
墓石の形状にも違いが見られます。
仏式で一般的な和型墓石は、上から竿石、上台石、中台石、芝台という四段構造が多いですが、神道のお墓では、角柱型の墓石や、先端が尖った「トキン型」と呼ばれる独特な形状の墓石が見られます。
また、お墓の敷地内には、仏式では見られない鳥居や玉垣(たまがき)、燈籠などが設けられることもあります。
これらは、お墓を神聖な空間として区別し、結界を示す意味合いがあります。
さらに、お墓を建てる時期も仏式とは異なります。
仏式では四十九日や百箇日、一周忌などに合わせて建墓することが多いですが、神道では五十日祭や一年祭を目途に建墓することが一般的です。
これらの違いは、神道の死生観や祖霊信仰に基づいています。
神道のお墓は、単に遺骨を納める場所というだけでなく、故人の御霊が家の守護神として鎮まる場所であり、家族が故人を敬い、感謝を捧げるための大切な聖域と位置づけられています。
納骨と祖霊舎(それいしゃ)の役割
神道における納骨は、仏式と同様に火葬後に遺骨をお墓(奥都城)に納める儀式です。
しかし、神道では故人の御霊は霊璽(れいじ)に宿ると考えるため、お墓はあくまで遺骨を納める場所であり、故人の御霊が常に鎮まっている場所は、自宅に祀る「祖霊舎(それいしゃ)」であると捉えられます。
祖霊舎は、仏式でいう仏壇にあたるもので、故人の御霊が宿る霊璽を安置するための祭壇です。
神棚とは別に設けられ、家の守護神となった祖先の御霊を祀るための大切な場所です。
祖霊舎には、霊璽の他に、神饌(米、酒、塩、水などのお供え物)、榊、燈明、玉串などを供えます。
日々の生活の中で、家族は祖霊舎に向かって手を合わせ、故人に感謝の気持ちを伝えたり、家系の安泰を祈ったりします。
納骨の時期は、五十日祭または一年祭を目途に行われるのが一般的です。
納骨の際には、「納骨祭(のうこつさい)」という儀式が執り行われます。
神職によって祝詞が奏上され、参列者は玉串奉奠を行います。
祖霊舎は、故人の御霊が常に家族と共にいる場所であり、日々の暮らしの中で故人との繋がりを感じ、感謝を伝えるための中心的な役割を果たします。
一方、お墓は、遺骨を納める場所であり、節目の祭祀や日常のお参りを通じて、故人や祖先との繋がりを確認し、敬意を表す場所です。
神道では、故人の御霊は祖霊舎に祀られる霊璽に宿り、家を見守ると考えられているため、祖霊舎は仏壇以上に故人の存在を身近に感じるための重要な存在と言えるでしょう。
年忌祭(ねんきさい)など死後の祭祀について
神道では、故人が亡くなった後の祭祀を「年忌祭(ねんきさい)」と呼び、仏式の年忌法要にあたります。
年忌祭は、故人の没後一年目の「一年祭」から始まり、三年祭、五年祭、十年祭、五十年祭など、特定の年に執り行われます。
これらの祭祀は、故人の御霊を慰め、感謝の気持ちを捧げ、家系の安泰と繁栄を祈るための大切な儀式です。
特に、一年祭は故人が家の守護神として完全に迎え入れられるための重要な節目と位置づけられています。
一年祭までは、五十日祭や百日祭などの節目にも祭祀が行われることがあります。
年忌祭は、自宅の祖霊舎の前や、斎場などで行われます。
神職によって祝詞が奏上され、故人の生前の功績が称えられ、参列者は玉串奉奠を行います。
祭祀の後には、直会(なおらい)と呼ばれる会食が行われるのが一般的です。
年忌祭をいつまで続けるかについては、明確な決まりはありませんが、一般的には五十年祭で「合祀祭(ごうしさい)」を行い、個別の霊璽を祖霊舎から移して他の祖霊と共に祀ることで、故人の霊が家の祖霊全体に合流したと考え、個別の年忌祭を終えることが多いようです。
しかし、家によってはそれ以降も祭祀を続ける場合もあります。
年忌祭以外にも、毎月一日や十五日、あるいは故人の命日などに、祖霊舎に手を合わせ、神饌を供えるなどの日々の祭祀が行われます。
これらの死後の祭祀を通じて、神道では故人の御霊を大切に祀り続け、家系の continuity を守り、祖先から子孫へと命と文化が受け継がれていくことの重要性を再確認します。
まとめ
神道における葬儀とお墓について、その基本的な考え方から具体的な儀式、費用、マナー、そして死後の祭祀に至るまでを詳しく解説しました。
神道では、故人は亡くなると家の守護神となり、子孫を見守ると考えられています。
このため、神葬祭は故人の御霊を清め、霊璽(れいじ)に移し、祖霊舎(それいしゃ)に祀るための重要な儀式です。
仏式とは異なり、読経や戒名はなく、神職による祝詞奏上や玉串奉奠が中心となります。
お墓は「奥都城(おくつき)」と呼ばれ、墓石には故人の生前の名前や諡(おくりな)が刻まれるなど、神道独自の特徴があります。
納骨後も、自宅の祖霊舎に故人の霊璽を祀り、日々の祭祀や年忌祭を通じて、故人の御霊を大切に祀り続けます。
神道における葬儀とお墓は、故人の御霊を神として迎え入れ、家系の continuity を守り、祖先を敬うという神道独自の死生観に基づいています。
これらの知識を持つことで、神道のご葬儀やお墓に対する理解が深まり、故人を偲ぶ大切な時間をより意義深いものにすることができるでしょう。
この記事が、神道における葬儀とお墓について知りたいと考えている皆様にとって、少しでもお役に立てば幸いです。