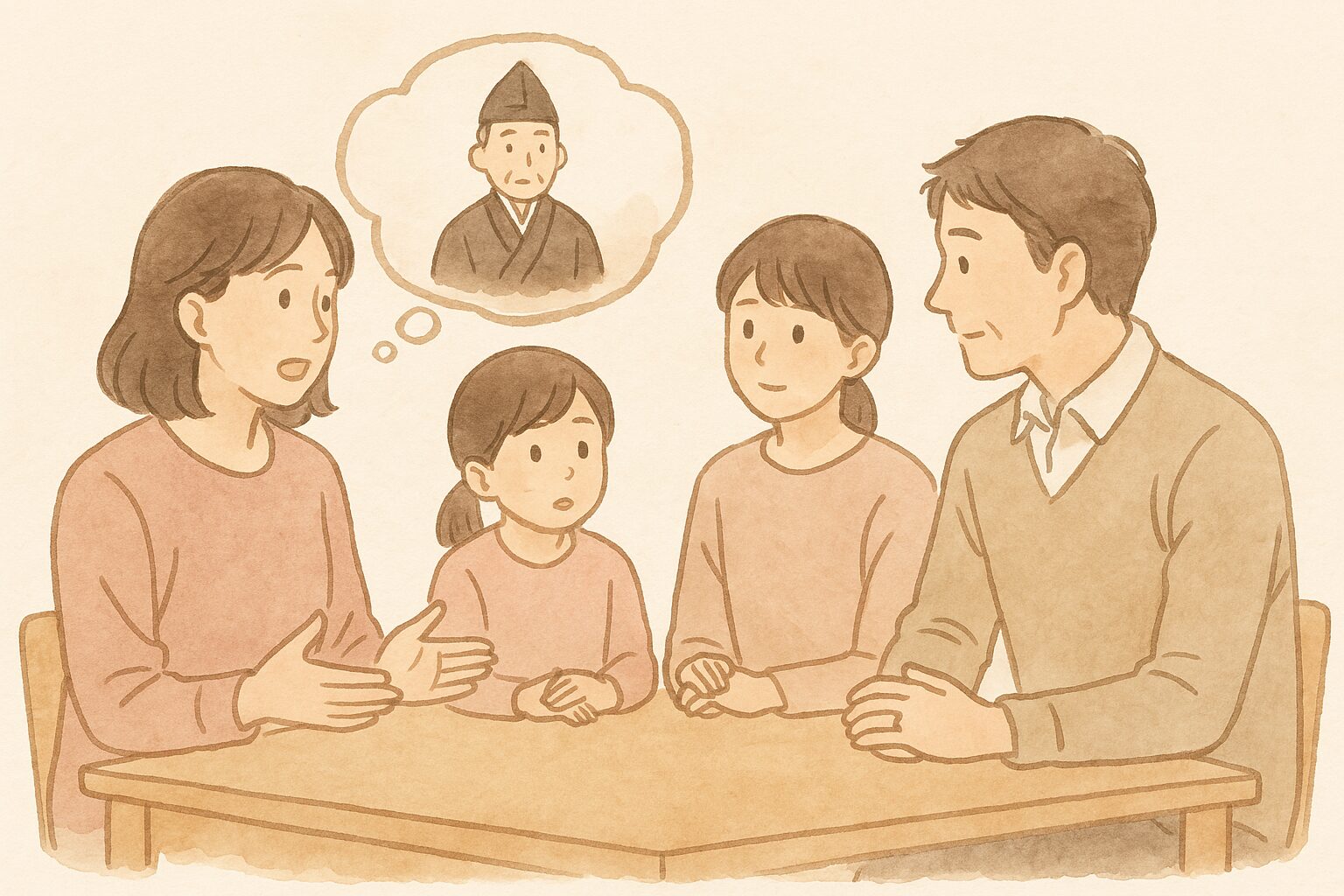大切なご家族との別れは、ただでさえ大きな悲しみの中にいる私たちに、様々な手続きや費用の負担を突きつけます。
特に葬儀にかかる費用は決して小さくなく、その後の相続税の申告と合わせて考えなければならないことも多くあります。
相続税の計算において、葬儀費用は「債務控除」として相続財産から差し引くことができる特例がありますが、一体何が控除できて、何ができないのか、手続きはどうすれば良いのか、多くの方が疑問に思われる点です。
また、せっかくの控除制度を知らずに利用できなかったり、誤った知識で申告して後から税務署から指摘を受けたりするようなことは避けたいものです。
この制度を賢く利用することで、相続税の負担を軽減し、少しでも心穏やかに故人を偲ぶ時間を過ごせるよう、相続税と葬儀費用賢く控除する方法について、分かりやすく丁寧にお伝えしていきます。
相続税の負担を軽減!葬儀費用を賢く控除するための基本
相続税の計算において、被相続人が亡くなった時点での相続財産の合計額から、借入金や未払金といった「債務」を差し引くことができます。
これと並んで、葬儀にかかった費用も特定の範囲内で「債務控除」として差し引くことが認められています。
これは、故人の最後の身辺整理にかかる費用を、相続財産から差し引くことを認めるという税法上の考え方に基づいています。
葬儀費用を相続財産から控除することで、相続税の課税対象となる財産を減らし、結果として相続税額を抑えることができるのです。
この控除は、相続人または包括受遺者が、実際に自己の財産から葬儀費用を負担した場合に適用を受けることができます。
例えば、相続人が複数いる場合でも、葬儀費用を実際に支払った人が、その支払った金額を控除できるのが原則です。
ただし、相続放棄をした人や、相続権を失った人は、たとえ葬儀費用を負担したとしても、この控除を受けることはできません。
相続税における葬儀費用の控除とは?
相続税法では、故人の死亡に伴って発生した特定の費用を、相続財産から差し引くことができると定めています。
この「特定の費用」の中に、通常行われる葬儀にかかる費用が含まれます。
なぜ葬儀費用が控除できるかというと、これは故人の最後の清算に関わる費用であり、相続財産から支払われるのが一般的であるため、相続財産を評価する際にこの費用を考慮に入れるべきだという考え方があるからです。
控除できる葬儀費用は、社会通念上、一般的に必要とされる範囲のものに限られます。
例えば、お通夜や告別式、火葬、埋葬など、一連の儀式にかかる費用がこれに該当します。
しかし、どのような費用が「一般的に必要とされる範囲」に含まれるのか、その線引きが曖昧だと感じる方もいらっしゃるかもしれません。
税法では具体的な項目を全て列挙しているわけではないため、判断に迷うケース