神道式葬儀とは何か――仏式とは異なる神道の死生観と儀礼の特徴
神道式葬儀は、「神式葬儀」や「神葬祭」とも呼ばれ、日本古来の神道に基づく葬儀形式です。
一般的に広く知られている仏式の葬儀とは儀礼や用語が大きく異なり、参列者にとっても戸惑いがちな点が多いものの、神道の世界観に根ざした意味ある儀式が数多くあります。
仏教が「輪廻転生」を前提とするのに対し、神道では死者は「祖霊(それい)」となり、子孫を見守る存在になると考えられています。
そのため、神道の葬儀は「死を穢れ」として忌避する側面と、「祖霊として祀る」という側面の二面性を持ち合わせています。
また、仏式では僧侶が読経を行うのに対し、神道では神職(しんしょく)が祝詞(のりと)を奏上し、神事を司るのが特徴です。
葬儀そのものが「祭り」として捉えられ、「神葬祭(しんそうさい)」という名称が使われる点にも、その思想が色濃く反映されています。
神棚を封じる「神棚封じ」や、玉串奉奠、榊の用意など、神道独特の風習が多く、初めて参列する方はその意味や所作を理解しておくと安心です。
このように、神道式葬儀は、故人を神として祀り、霊を清らかに迎えるという思想に基づいた、静かで厳かな儀式です。
神道における死のとらえ方と「祖霊」の概念
神道では、「死」は決して終わりではありません。
人は死後、「祖霊」となって家族を見守る存在になると考えられています。
これは仏教における極楽浄土とは異なり、「霊がこの世に留まり、家や子孫と共にある」という、日本人独特の死生観の現れでもあります。
その祖霊は、家庭内の「祖霊舎(それいしゃ)」に霊璽(れいじ)という木の位牌のようなものを収めて祀られ、日々の生活の中で敬意を持って迎えられます。
仏教で言う位牌や仏壇とは違い、神道では「穢れを遠ざけ、清らかに祀る」ことが重要視されます。
こうした文化背景があるため、神道式の葬儀は、清浄な儀式として構成されるのです。
神葬祭と霊祭の意味と違い――神式ならではの呼び方に注目
神道の葬儀では、仏式でいう「通夜」や「告別式」にあたるものを「神葬祭(しんそうさい)」と呼びます。
これは単なる通過儀礼ではなく、故人の魂を祖霊として迎えるための重要な神事とされています。
その後、一定期間を経て行われる追悼の儀式が「霊祭(れいさい)」です。
仏教における年忌法要に近い存在ですが、こちらも読経ではなく祝詞によって執り行われます。
たとえば「十日祭」「五十日祭」「一年祭」「十年祭」などの節目で実施され、家族や親族が霊を思い、感謝と敬意を伝える場となります。
このように、神道では故人を「仏」ではなく「神(祖霊)」として祀ることから、葬儀全体が神祭りの一環として位置づけられているのが特徴です。
名称や形式が異なるため、仏式との違いをあらかじめ知っておくことで、参列者としての理解も深まります。
仏具を使わない神道式――焼香の代わりに玉串を捧げる理由
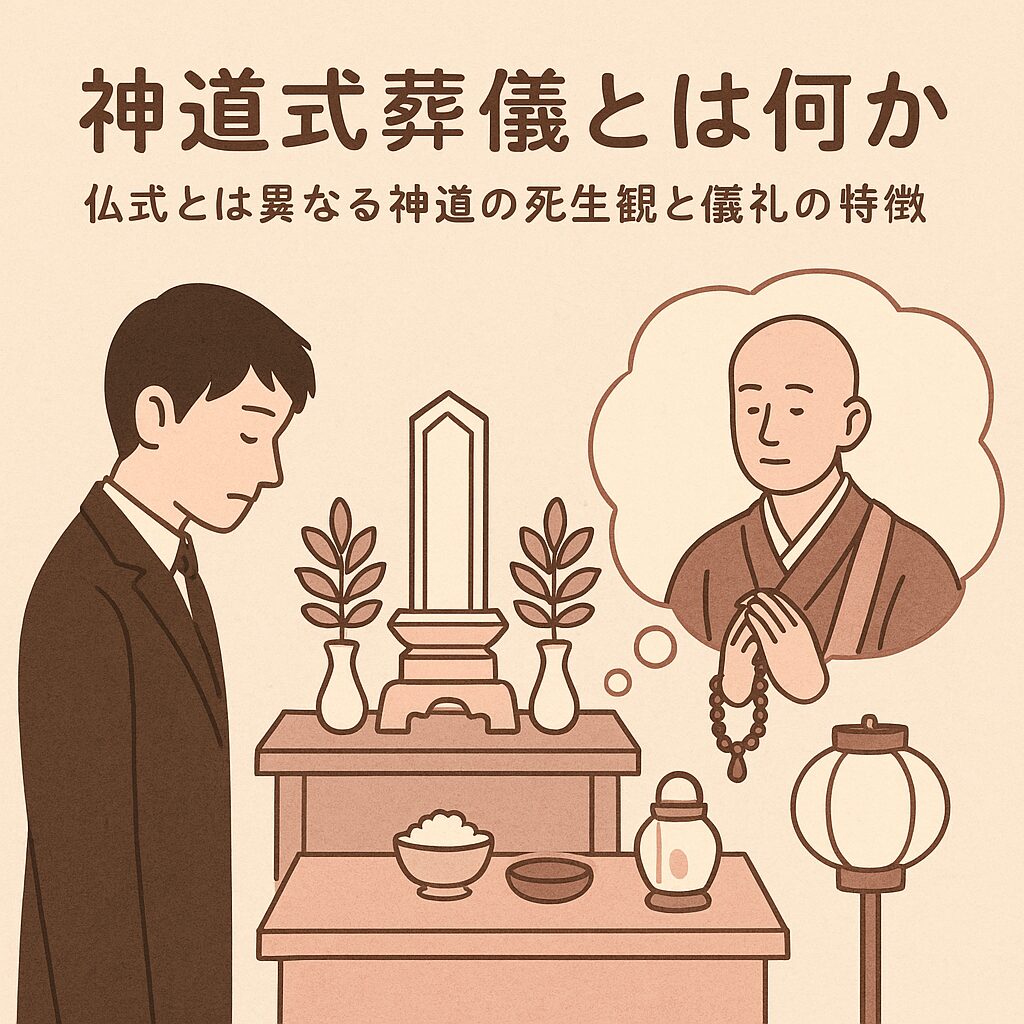
神道式葬儀では、仏式のように焼香を行うことはありません。
その代わりに行われるのが「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」という神道ならではの儀式です。
玉串とは、榊(さかき)の枝に白い紙を結んだもので、榊は神と人との境をつなぐ神聖な木とされています。
参列者はこの玉串を神前に捧げ、二礼二拍手一礼(あるいは拍手なしの黙礼)という作法で敬意を示します。
これは神に祈りを捧げるときと同様の形式であり、焼香とは異なる「神に向き合う」姿勢が大切とされます。
また、神道では香の煙を用いることはなく、香炉や数珠などの仏具も使用しません。
そのため、仏教に慣れている方にとっては違和感を覚えることもありますが、神道の形式を尊重する意味でも、あらかじめ玉串奉奠の流れを知っておくことが望ましいです。
葬儀の場で不安なく動けるように、事前に予備知識を持つことは大きな助けとなります。
神道式葬儀の流れと準備――神職による神事の進行と遺族の心得

神道式葬儀では、一連の儀礼が「神事」として厳粛に執り行われるのが特徴です。
仏式のように読経や戒名がない代わりに、神職による祝詞奏上や玉串奉奠など、神に向き合う所作が中心となります。
葬儀は大まかに「通夜祭(または遷霊祭)」「葬場祭」「火葬祭」「帰家祭」などで構成され、これらの流れを総称して「神葬祭」と呼びます。
また、仏式葬儀と違い、神道では「死」は穢れとされるため、遺族や参列者はその考えを理解したうえで行動することが求められます。
儀式の進行や作法に迷いがある場合でも、神職が丁寧に導いてくれるため、事前に不安を取り除いておくことが大切です。
葬儀の前段階として、神棚封じや霊前灯籠の設置など、神道ならではの準備も欠かせません。
こうした細やかな所作には、霊を敬い、清らかに送り出すという強い意味が込められています。
神道式葬儀をきちんと執り行うには、遺族側にも一定の理解と準備が求められるのです。
神職と斎主の役割――神道の葬儀における進行役とは
神道葬儀では、儀式全体を統括するのが「神職(しんしょく)」であり、その中でも中心となるのが「斎主(さいしゅ)」や「祭主(さいしゅ)」と呼ばれる存在です。
神社に所属する神職が担当することもあれば、家にゆかりのある神社から派遣される場合もあります。
斎主は祝詞の奏上、玉串奉奠の導入、手水の儀などを厳粛に取り仕切り、葬儀の一連の流れを正しく神式に則って進行させる役目を担います。
また、参列者に対して所作や礼儀の説明を行うことも多く、初めて神道式に参列する人でも安心できるよう配慮される場面もあります。
こうした神職の存在があることで、葬儀全体が神聖かつ秩序正しく運営されるのが、神道式ならではの特長です。
神棚封じや霊前灯籠など、神道ならではの準備と設え
神道式の葬儀においては、葬儀前の準備段階で行う「神棚封じ(かみだなふうじ)」が重要な意味を持ちます。
神棚は本来、家庭内の神聖な場所であり、そこに死という「穢れ」が及ぶのを防ぐために、白紙で神棚を覆い、一時的に拝礼を控える処置を施します。
また、故人を祀る場には「霊前灯籠(れいぜんとうろう)」や榊を飾り、清らかで荘厳な空間を整えることが神道葬儀の基本です。
仏教のような線香や仏具は使われず、全体的にシンプルでありながら厳粛な設えが重視されます。
これらの準備は、単に形式的なものではなく、霊を敬い、清浄な状態で見送るための大切な儀式の一部として位置づけられており、遺族としても丁寧に行う必要があります。
手水・玉串奉奠・斎場での作法――神道葬儀にふさわしい所作と礼儀
神道式葬儀の現場では、最初に行う「手水(ちょうず)」の作法が重要視されます。
これは神社に参拝する際と同様に、手と口を清めてから神前に進むという神道の基本的な儀礼です。
葬儀会場にも手水場が設けられることがあり、参列者はここで身を清めてから会場に入ります。
その後の儀式では、焼香の代わりに「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」が行われ、参列者一人ひとりが榊を神前に捧げ、黙礼または無音の二拝二拍手一拝を行うのが通例です。
この所作には「故人の霊を神として迎え入れる」という深い意味が込められています。
また、服装についても注意が必要です。
神道では家紋入りの白い喪服や、黒留袖、紋付き袴などが正式とされることがあり、仏式よりもやや格式の高い礼装が求められる場面もあります。
ただし、近年は略式のブラックフォーマルでも問題ない場合が増えてきているため、神社や斎場の方針を確認するのが安心です。
参列者が知っておきたい神道式葬儀のマナーと注意点

神道式葬儀に参列する際、仏式との違いに戸惑う人は少なくありません。
特に初めての経験となると、どのような服装がふさわしいのか、焼香の代わりに何をするのかといった基本的なマナーに不安を感じる方も多いでしょう。
神道では死を「穢れ」と捉えるため、清浄さや礼儀が特に重要視されます。
また、儀式の進行も仏教のような読経ではなく、祝詞奏上や玉串奉奠といった神事にのっとった流れとなるため、参列者にもそれなりの心構えが求められます。
仏具が置かれていない祭壇や、榊の葉が飾られた神前のしつらえを見て戸惑わないように、事前に神道式葬儀ならではのマナーを理解しておくことが大切です。
服装の選び方、玉串奉奠の作法、そして仏教式との混同を避けるポイントなど、ここでは参列者が安心して臨めるような実践的なマナーをわかりやすく解説していきます。
服装の選び方――家紋や色に注意する神道の礼装とは
神道式葬儀では、「清浄さ」を重んじる精神に則った服装が求められます。
基本的には仏式と同様に、黒を基調とした喪服で問題ありませんが、格式の高い葬儀では、特に家紋入りの正喪服が選ばれることもあります。
例えば、男性であれば黒紋付羽織袴に白足袋、女性であれば五つ紋付きの黒無地の和服や黒留袖が正式な礼装とされます。
近年は略式喪服でも許容される傾向にありますが、神社関係者が関わる葬儀や本家筋の儀式では、服装マナーに厳格な場合もあるため、事前に確認しておくのが安心です。
また、装飾が派手すぎないこと、光沢素材を避けることなども重要なポイントです。
さらに、神道では「家紋」そのものにも意味が込められており、先祖代々の血縁や家の歴史に対する敬意を示す場面でもあるため、家紋の入った礼装を用意する家庭も少なくありません。
玉串奉奠の手順と意味――参列時の心構えと正しい作法
神道式葬儀で最も重要な所作のひとつが「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」です。
これは、神前に玉串を捧げることで、故人の魂に敬意と感謝を表す儀式であり、焼香とはまったく異なる形式をとります。
玉串は榊の枝に紙垂(しで)を結んだもので、神と人との間をつなぐ神聖な道具とされています。
参列者は玉串を受け取り、祭壇の前に進み、胸の高さで持って回転させ、根元が神前を向くようにして供えます。
その後、黙礼や二拝二拍手一拝を行うのが一般的な流れです。
初めてこの作法に触れる方には難しく感じられるかもしれませんが、神職が誘導してくれることが多いため、落ち着いて流れに従うことが大切です。
また、玉串奉奠はあくまで敬意を示す儀式なので、心を込めて行うことが何よりも重要です。
仏教式との混同を避けるために気をつけたいポイント
神道式葬儀では、仏教式の習慣や道具が使用されないため、混同によるマナー違反には特に注意が必要です。
たとえば、数珠を手に持ったまま参列する、香典袋に「御仏前」と記載してしまうといった行為は、神式では適切ではありません。
神道における葬儀では、仏壇や仏具は一切使わず、神棚や祖霊舎が中心となり、神事として祝詞を捧げる点が特徴的です。
香を焚くこともなく、代わりに玉串を捧げるため、焼香台も存在しません。
このような違いを理解せずに参列すると、意図せずして場の空気を乱すことにもなりかねません。
また、仏式では「拝む」動作が一般的ですが、神式では「祈る」よりも「敬意を表す」ことが主目的となるため、姿勢や表情にも気を配る必要があります。
事前に神式の特徴を押さえておけば、自然な振る舞いで故人と向き合うことができるでしょう。









