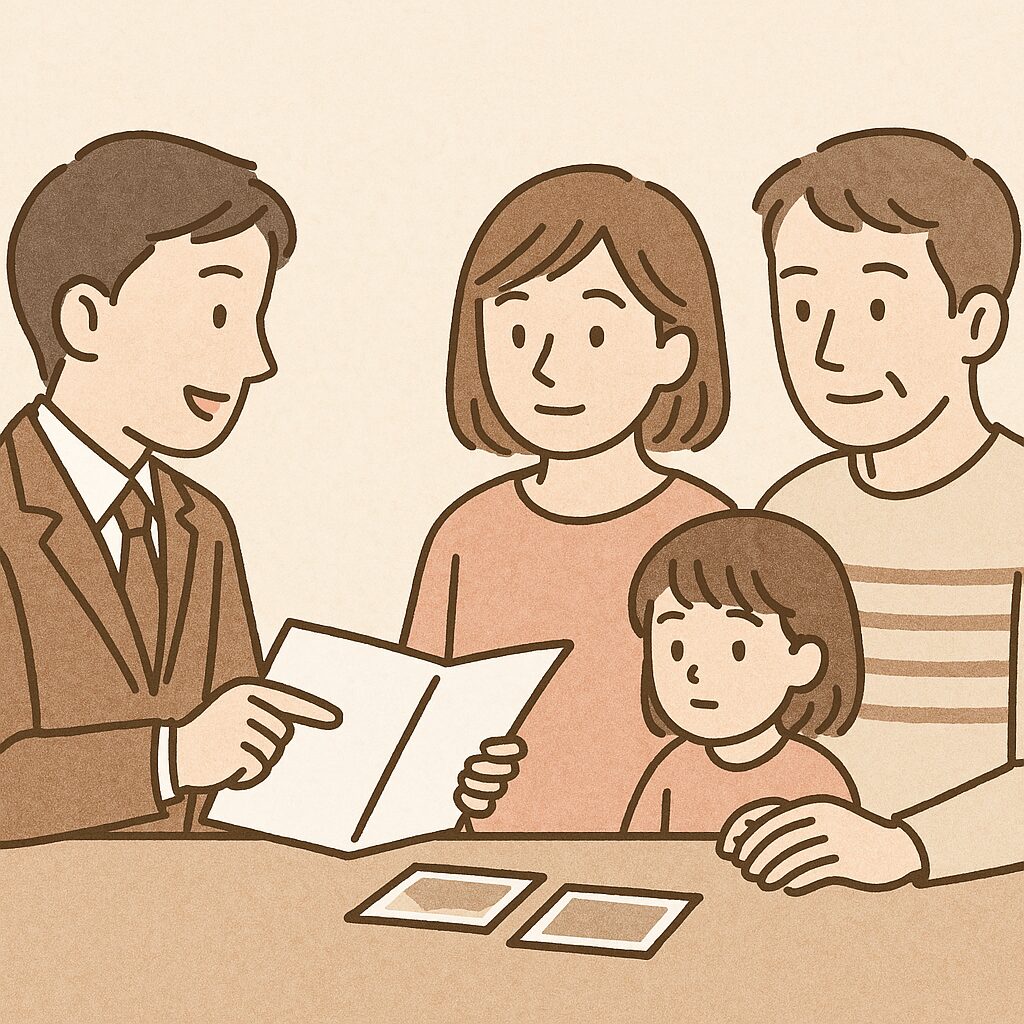大切な方が旅立たれた時、深い悲しみの中で様々な準備に追われることになります。
その一つが、葬儀に参列する際の服装ではないでしょうか。
特に、どのようなスーツを着れば良いのか、普段着ているビジネススーツでは失礼にあたるのかなど、多くの疑問が浮かぶかもしれません。
葬式に着用するスーツの種類について、正しく理解しておくことは、故人様やご遺族に失礼なく、また落ち着いてお別れをするために非常に重要です。
この度は、急な訃報に際しても慌てず、適切な服装で参列できるよう、葬儀におけるスーツの選び方やマナーについて詳しく解説していきます。
どうぞ、最後までお読みいただき、いざという時の備えとしていただければ幸いです。
葬儀にふさわしい「喪服」とは?基本的な知識
葬儀や告別式に参列する際の服装には、明確なマナーが存在します。
一般的に「喪服」と呼ばれる服装がこれにあたりますが、実は一口に喪服と言ってもいくつか種類があることをご存知でしょうか。
最も格式が高いのは「正喪服」で、これは主に喪主や親族といった、葬儀を取り仕切る立場の人が着用します。
男性ならモーニングコートや和装、女性ならブラックフォーマルの中でも最も格式高いデザインのワンピースやアンサンブルなどがこれにあたります。
しかし、一般の会葬者が正喪服を着用することはほとんどありません。
私たちが普段「喪服」として認識しているのは、実は「準喪服」と呼ばれるものです。
これは、正喪服に次ぐ格式を持ち、喪主を含む遺族だけでなく、一般の会葬者も通夜や告別式、法要などで着用できる最も一般的な喪服です。
そして、もう一つ「略喪服」というものがあります。
これは、急な弔問や仮通夜、お別れ会などで着用される、地味な色の平服を指します。
このように、喪服には格式があり、参列する立場や場面によって適切な服装が異なりますが、一般会葬者として葬儀に参列する場合は、基本的に準喪服である「ブラックスーツ(男性)」または「ブラックフォーマル(女性)」を着用するのがマナーとされています。
特に、準喪服は黒色の無地で、光沢のない生地を選び、デザインも控えめなものが基本となります。
この基本を知っておくことが、葬儀の服装選びの第一歩となります。
男性の喪服:ブラックスーツの選び方
男性が葬儀で着用する準喪服は、一般的に「ブラックスーツ」と呼ばれます。
しかし、普段ビジネスシーンで着ている黒いスーツとは明確な違いがあることを理解しておく必要があります。
ビジネス用の黒いスーツは、生地にわずかに光沢があったり、細かな織り柄が入っていたりすることがありますが、喪服としてのブラックスーツは、漆黒に近い深い黒色で、光沢が一切なく、無地の生地が基本です。
これは、光を反射せず、故人様への哀悼の意を静かに表すためとされています。
デザインも、シングルまたはダブルのブレストで、シンプルなものが一般的です。
シングルの場合は二つボタン、ダブルの場合は四つボタン二つ掛けや六つボタン二つ掛けが主流です。
スラックスはシングル仕上げが基本ですが、最近はダブル仕上げでも許容される場面もありますが、より正式な場ではシングルが無難でしょう。
素材は、オールシーズン着用できるウール素材が一般的ですが、夏場はサマーウールやポリエステル混紡の通気性の良いもの、冬場は厚手のウールやカシミヤ混紡など、季節に応じた素材感のものを選ぶと快適に過ごせます。
購入する際は、ビジネススーツ専門店ではなく、フォーマルウェア専門店や百貨店のフォーマルコーナーで選ぶことを強くおすすめします。
専門店の店員さんは、喪服とビジネススーツの違いや、正しい着こなしについて詳しい知識を持っています。
知人の体験談ですが、急な訃報で慌てて量販店で黒いスーツを買ったところ、後からフォーマル専門店の方に「それはビジネス用の黒ですね」と指摘され、恥ずかしい思いをしたという話を聞きました。
やはり、いざという時に迷わないよう、一着は本物のブラックスーツを用意しておくことが大切です。
試着する際は、肩幅や着丈、袖丈などが体に合っているかを確認し、清潔感のある着こなしができるサイズを選びましょう。
女性の喪服:ブラックフォーマルの選び方
女性が葬儀で着用する準喪服は「ブラックフォーマル」と呼ばれ、男性のブラックスーツと同様に、漆黒に近い深い黒色の生地が基本です。
デザインは、ワンピース、アンサンブル(ワンピースとジャケットの組み合わせ)、またはスーツ(ジャケットとスカートやパンツの組み合わせ)などがあります。
最も一般的で間違いがないのは、ワンピースにジャケットを羽織るアンサンブルスタイルです。
ワンピースは袖があるデザインを選ぶのがマナーとされており、夏場でも半袖以上のものを選び、ノースリーブは避けるのが無難です。
スカート丈は、正座した際に膝が隠れる程度の長さが適切です。
最近ではパンツスーツのブラックフォーマルも増えてきており、動きやすさや寒さ対策の観点から選ばれる方もいらっしゃいますが、より伝統的な場や年配の方が多い場では、スカートスタイルの方が無難かもしれません。
素材は、光沢のないウールやポリエステル、トリアセテートなどが使われます。
夏場は薄手で通気性の良いもの、冬場は厚手のものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。
デザインは、フリルやレースなどの装飾が控えめで、シンプルで上品なものを選びます。
胸元が開きすぎているデザインや、体のラインを強調するようなデザインは避けるべきです。
フォーマルウェア専門店の店員さんから伺った一次情報ですが、最近のブラックフォーマルはデザインのバリエーションが増えていますが、やはり基本は「露出が少なく、体の線を拾いすぎない、シンプルなデザイン」を選ぶのが最も安心できるとのことでした。
特に、急な弔問などでは、手持ちのシンプルな黒いワンピースに黒いカーディガンなどを羽織る略喪服で対応することもありますが、通夜や告別式に参列する場合は、やはり一着きちんとしたブラックフォーマルを用意しておくと、急な時でも慌てずに済みます。
購入する際は、試着をしてサイズ感をしっかり確認し、長時間の着用でも疲れにくい、着心地の良いものを選ぶことが大切です。
子供の喪服:学生服または地味な服装
お子さんが葬儀に参列する場合の服装は、大人の喪服とは少し考え方が異なります。
もしお子さんが学生であれば、学校の制服を着用するのが最も適切で、正式な喪服となります。
制服は学校が定めた標準服であり、冠婚葬祭の場にも対応できる服装として認められています。
特に指定がなければ、夏服、冬服どちらでも構いませんが、その時期に合った清潔感のある制服を選びましょう。
制服がない場合や、まだ未就学のお子さんの場合は、地味な色の服装を選びます。
色は黒、紺、グレー、白などが基本です。
男の子であれば、白いシャツに黒や紺のズボン、地味な色のジャケットやカーディガンなどを合わせます。
女の子であれば、白いブラウスに黒や紺、グレーのスカートやワンピースなどを選びます。
キャラクターものや派手な色、柄の入った服は避けましょう。
靴も、光沢のない地味な色のものを選びます。
学校指定の白い運動靴や、黒や紺のシンプルな靴などが適しています。
エナメル素材や派手な装飾のある靴は避けた方が良いでしょう。
靴下も、白、黒、紺などの地味な色を選びます。
小さなお子さんの場合、急に用意するのが難しいこともありますので、普段から黒や紺、グレーなどの地味な色のシンプルな服を数着用意しておくと安心です。
特に、お別れ会など、格式ばらない場であれば、地味な色の普段着でも構いませんが、通夜や告別式に参列する場合は、できるだけフォーマルに近い服装を心がけることが大切です。
子供の服装で一番重要なのは、清潔感があることと、派手な装飾や色は避けること、そしてお子さん自身が快適に過ごせる服装であることでしょう。
喪服以外でも大丈夫?準喪服・略喪服の考え方
葬儀に参列する際の服装は、原則として準喪服(男性はブラックスーツ、女性はブラックフォーマル)が基本であることをお伝えしました。
しかし、様々な状況から、必ずしも準喪服を用意できない場合や、準喪服以外の服装が適切な場面も存在します。
例えば、急な訃報で準喪服を用意する時間がない、あるいは家族葬や平服での参列が指定されている場合などです。
このような場合にどう対応すれば良いのか、準喪服以外の服装、つまり「略喪服」やそれに準ずる服装について理解しておくことは、いざという時に非常に役立ちます。
略喪服は、準喪服よりも格式が下がりますが、失礼にあたらない範囲での地味な服装を指します。
具体的には、ダークカラーのビジネススーツや、地味な色のワンピースなどがこれにあたります。
重要なのは、場面に応じた適切な服装を選ぶ判断力と、故人様やご遺族への配慮の気持ちです。
全ての葬儀が大規模で格式ばったものであるとは限りません。
家族葬のようにごく身近な人のみで行われる場合や、故人様の遺志で「平服でお越しください」と案内される場合もあります。
このような多様な葬儀の形式に合わせて、服装も柔軟に対応する必要があります。
ただし、「平服」と指定されていても、普段着ているようなカジュアルな服装で参列するのはマナー違反です。
この場合の「平服」は、「喪服でなくて構いませんが、礼節をわきまえた地味な服装でお越しください」という意味合いが強いです。
急な訃報!手持ちのダークスーツで代用する場合の注意点
急な訃報を受けた際、手元に準喪服がないという状況は少なくありません。
特に、出張先や旅行中に訃報を受けたり、学生でまだ喪服を持っていなかったりする場合などです。
このような緊急時には、略喪服として手持ちのダークカラーのスーツで代用することが許容される場合があります。
男性であれば、黒、紺、濃いグレーなどの無地のビジネススーツがこれにあたります。
女性であれば、黒、紺、濃いグレーなどの無地のワンピースやアンサンブル、またはパンツスーツなどが考えられます。
ただし、ダークカラーのスーツであれば何でも良いというわけではありません。
いくつかの注意点があります。
まず、色はできるだけ濃いものを選び、光沢のある生地や明るすぎる色は避けてください。
紺色でも、限りなく黒に近い濃紺が望ましいでしょう。
次に、柄は絶対に避けてください。
ストライプやチェックなどの柄が入ったビジネススーツは、どんなに色が地味でも喪服の代用としては不適切です。
無地のものを選びましょう。
また、シャツやブラウスは白無地が基本です。
ネクタイや小物類も、後述するマナーに沿ったものを選び、全体として地味で落ち着いた印象になるように心がけます。
靴も、光沢のない黒い革靴やパンプスを選びます。
知人の例ですが、急な出張先で訃報を受け、手持ちの濃紺の無地スーツで参列したそうです。
その際、白無地のシャツに黒無地のネクタイ、黒い靴を選び、全体を落ち着いたトーンにまとめたところ、特に問題なく参列できたとのことでした。
ただし、これはあくまで「急な場合」の代用策であり、正式な場ではやはり準喪服を着用するのが望ましいです。
もし時間があれば、葬儀会場の近くでレンタルするなど、準喪服を準備する努力をすることも大切です。
家族葬や平服指定の場合の服装マナー
近年増加している家族葬や、遺族から「平服でお越しください」と案内があった場合の服装は、準喪服が必須ではありません。
しかし、前述したように、「平服」=「普段着」ではないため、服装選びには注意が必要です。
家族葬の場合、一般葬に比べて少人数で行われることが多く、比較的アットホームな雰囲気で行われることもありますが、故人様を偲び、ご遺族に寄り添う場であることに変わりはありません。
そのため、準喪服を着用しても全く問題ありませんし、むしろ失礼にあたることはありません。
もし準喪服を持っているのであれば、着用するのが最も無難です。
一方、「平服で」と指定された場合は、略喪服を着用するのが適切です。
男性であれば、ダークカラー(黒、紺、濃いグレーなど)の無地のスーツに、白無地のシャツ、地味な色のネクタイを合わせます。
ネクタイの色は黒が基本ですが、濃い紺やグレーなどでも許容される場合があります。
女性であれば、ダークカラーの無地のワンピースやアンサンブル、またはパンツスーツなどが良いでしょう。
いずれの場合も、派手な色や柄、光沢のある生地、露出の多いデザインは避けるのが鉄則です。
アクセサリーも、結婚指輪以外は外すか、パールの一連ネックレスなど控えめなものを選びます。
フォーマルウェア専門店の方のお話では、「平服で」と言われた場合でも、「喪服に準ずる、落ち着いた服装」と解釈するのが最も安全とのことでした。
例えば、男性がノーネクタイで参列したり、女性が明るい色のカーディガンを着たりするのは、たとえ平服指定であっても避けるべきです。
故人様やご遺族への敬意を表すため、あくまでも控えめで地味な服装を心がけることが、家族葬や平服指定の場合の重要なマナーとなります。
スーツ以外で気をつけたい小物と身だしなみ
葬儀に参列する際の服装は、スーツそのものだけでなく、それに合わせる小物類や全体の身だしなみも非常に重要です。
どんなにきちんとした喪服を着ていても、小物選びや身だしなみに気を配らないと、全体の印象が崩れてしまい、マナー違反と見なされてしまう可能性があります。
特に、ネクタイ、シャツ、靴、バッグ、アクセサリー、メイク、ヘアスタイルなどは、葬儀の場にふさわしいものを選ぶ必要があります。
これらの小物や身だしなみは、故人様への哀悼の意を表し、ご遺族に配慮するためのものです。
派手なものや華美なものは避け、控えめで落ち着いた印象を与えることが基本となります。
例えば、男性のネクタイは黒無地が鉄則ですが、素材や結び方にもマナーがあります。
女性のバッグは、殺生を連想させる革製品や毛皮製品は避けるべきとされています。
また、アクセサリーは、結婚指輪以外は基本的に外すか、パールなど控えめなものに限られます。
メイクやヘアスタイルも、派手な印象にならないように注意が必要です。
これらの小物や身だしなみに関するマナーは、地域や宗派、あるいはご遺族の意向によって多少異なる場合もありますが、一般的に広く受け入れられている基本的なルールを知っておくことが大切です。
スーツだけでなく、頭からつま先まで、全身のバランスを考えて準備することが、葬儀における完璧な身だしなみにつながります。
ネクタイ、シャツ、靴、バッグ:NGなものとOKなもの
男性の場合、スーツに合わせる小物として特に重要なのが、ネクタイ、シャツ、そして靴です。
ネクタイは、光沢のない黒無地が唯一の選択肢です。
素材はシルクやポリエステルなどが一般的ですが、織り柄が入っていない無地のものを選びます。
結び方は、ディンプル(結び目の下のくぼみ)を作らないプレーンノットで、結び目が小さくまとまるようにするのが一般的です。
シャツは、白無地のレギュラーカラーまたはワイドカラーのワイシャツを選びます。
ボタンダウンシャツはカジュアルな印象になるため、避けるのが無難です。
カフスボタンはつけません。
靴は、光沢のない黒い革靴で、内羽根式のストレートチップまたはプレーントゥが最もフォーマルとされています。
エナメル素材や爬虫類革、スエード素材の靴は避けましょう。
靴下は、黒無地のビジネスソックスを選びます。
バッグを持つ場合は、黒無地のセカンドバッグやクラッチバッグなどが適しています。
ビジネスバッグで参列する場合は、黒無地でシンプルなデザインのものを選び、中に派手なものが見えないように注意します。
女性の場合、スーツやワンピースに合わせる小物として、靴とバッグが重要です。
靴は、光沢のない黒いパンプスを選びます。
ヒールは高すぎず、安定感のあるもの(3〜5cm程度が目安)が良いでしょう。
ストラップ付きでも構いませんが、オープントゥやサンダル、ミュール、ブーツなどは不適切です。
ストッキングは、肌色のものか、黒いものを選びます。
黒いストッキングは、濃いデニールのものはカジュアルに見えることがあるため、薄手のもの(30デニール以下が目安)が無難です。
バッグは、光沢のない布製または合皮製の黒いハンドバッグを選びます。
殺生を連想させる革製品や毛皮製品は避けるのがマナーとされていますが、最近は黒無地のシンプルな革製バッグであれば許容される場合もあります。
ただし、ワニ革やヘビ革、エナメル素材、ブランドのロゴが大きく入ったバッグは避けるべきです。
サブバッグが必要な場合は、黒無地の布製トートバッグなどを使います。
これらの小物選びは、全体の印象を左右するため、細部まで気を配ることが大切です。
アクセサリー、メイク、ヘアスタイル:控えめが基本
葬儀におけるアクセサリー、メイク、ヘアスタイルも、控えめであることが基本です。
アクセサリーは、結婚指輪以外は基本的に外すのがマナーとされています。
もしつける場合は、パールの一連ネックレスや一粒のイヤリング(ピアス)など、控えめで上品なものに限られます。
二連以上のネックレスは「不幸が重なる」という連想をさせるため、避けるべきとされています。
ダイヤモンドや色石、ゴールド素材のアクセサリーなど、光沢があったり華美に見えるものは不適切です。
メイクは、ナチュラルメイクが基本です。
派手なアイシャドウやリップ、チークは避け、肌色に近い落ち着いた色合いで、控えめに仕上げます。
特に、涙で崩れてしまう可能性もあるため、ウォータープルーフのマスカラなどを使用する際は注意が必要です。
ノーメイクでも問題ありませんが、肌荒れなどが気になる場合は、薄くファンデーションを塗る程度に留めましょう。
ヘアスタイルは、清潔感があり、顔にかからないようにまとめるのが一般的です。
長い髪は、低い位置で一つに結ぶか、シニヨンなどにまとめます。
前髪が長い場合は、ピンで留めるか横に流すなどして、顔にかからないようにします。
明るい髪色の方は、一時的に暗めの色に戻すか、ヘアスプレーなどで目立たなくする配慮も必要かもしれません。
ヘアアクセサリーは、黒無地のシンプルなバレッタやゴムなどを使用し、飾りのついたものや光沢のあるものは避けます。
全体として、地味で落ち着いた印象を心がけることが、葬儀の場にふさわしい身だしなみとなります。
これは、故人様との別れを惜しみ、ご遺族の悲しみに寄り添う気持ちを表すための重要な配慮なのです。
喪服を準備する方法:購入?レンタル?それとも?
葬儀に参列するための喪服を準備する方法は、大きく分けて「購入」「レンタル」「手持ちの服で代用」の3つがあります。
それぞれの方法にはメリットとデメリットがあり、ご自身の状況やライフスタイル、予算などに合わせて最適な方法を選ぶことが大切です。
例えば、今後も葬儀に参列する機会が多いと予想される方や、急な訃報に備えておきたいという方は、一着きちんとした喪服を購入しておくと安心です。
一方、喪服を着用する機会が infrequent な方や、一時的に必要になったという方は、レンタルを利用するのも賢い選択肢です。
また、前述のように、急な場合や平服指定の場合は、手持ちのダークカラーの服で代用することもあります。
どの方法を選ぶにしても、いざという時に慌てないよう、事前にそれぞれの方法について知っておくことが重要です。
特に、購入やレンタルを検討する場合は、サイズ選びやデザイン選びに時間をかけられるよう、余裕を持って準備を進めることをお勧めします。
葬儀は予期せぬタイミングで訪れることが多いため、「いつか必要になるかもしれない」という意識を持って、準備について考えておくことが、心のゆとりにも繋がります。
購入のメリット・デメリットと選び方のポイント
喪服を購入する最大のメリットは、自分の体型に合ったものをいつでもすぐに着用できるという点です。
急な訃報に際しても慌てることなく、失礼のない服装で駆けつけることができます。
また、自分専用の喪服を持つことで、お手入れをしながら長く大切に着ることができます。
デザインや素材も豊富にある中から、自分の好みや年齢、体型に合ったものを選ぶことができるのも魅力です。
特に、フォーマルウェアは流行に左右されにくいため、一度良いものを購入すれば、長期間にわたって着用できます。
デメリットとしては、初期費用がかかること、そして保管場所が必要になることが挙げられます。
また、体型の変化によって着られなくなる可能性もゼロではありません。
喪服を選ぶ際のポイントはいくつかあります。
まず、生地の色と光沢です。
男性のブラックスーツも女性のブラックフォーマルも、漆黒に近い深い黒色で、光沢のない生地を選びます。
次に、デザインです。
男性はシングルまたはダブルのシンプルなブレスト、女性は露出が少なく、体のラインを拾いすぎないワンピースやアンサンブルが基本です。
スカート丈は、正座した際に膝が隠れる長さを選びます。
素材は、オールシーズン着用できるウール素材が一般的ですが、夏用や冬用など、季節に合わせた素材感のものを用意するとより快適です。
最後に、サイズ感です。
試着をして、肩幅、着丈、袖丈、ウエストなどが体に合っているかを確認します。
特に、喪服は少しゆったりめのサイズを選ぶ方が多い傾向にあります。
購入場所としては、百貨店のフォーマルウェア売り場や、フォーマルウェア専門店がおすすめです。
専門知識を持った店員さんが、適切なサイズやデザイン選び、お手入れ方法などについて丁寧にアドバイスしてくれます。
価格帯は幅広くありますが、品質の良いものを選べば、長く着用できるため、結果的にコストパフォーマンスが良い場合もあります。
レンタルのメリット・デメリットと利用シーン
喪服をレンタルする最大のメリットは、購入するよりも費用を抑えられるという点です。
特に、喪服を着用する機会が infrequent な方や、一時的に必要になったという方にとっては、経済的な負担が少なく済みます。
また、保管場所を気にする必要がなく、クリーニングの手間も省けるのも利点です。
体型の変化を気にすることなく、その都度ぴったりのサイズを選べるのもレンタルの魅力でしょう。
デメリットとしては、急な訃報の場合に対応しにくい可能性があるという点です。
レンタルショップによっては即日対応が難しかったり、希望のサイズやデザインが在庫切れだったりする場合があります。
また、レンタル期間が決まっているため、追加料金が発生しないよう返却期日を気にしなければなりません。
さらに、多くの人が着用したものであるため、新品のような状態ではない場合もあります。
レンタルが向いている利用シーンとしては、急な弔事で手持ちの服がない場合や、子供の成長が早くすぐにサイズが変わってしまう場合、あるいは海外からの参列で荷物を減らしたい場合などが挙げられます。
最近では、インターネットでレンタルできるサービスも増えており、自宅に配送してもらうことも可能です。
ただし、ネットレンタルの場合は試着ができないため、サイズ選びには注意が必要です。
レンタルする際は、利用日の数日前には手元に届くように手配し、試着をしてサイズや状態を確認しておくことをおすすめします。
もしサイズが合わなかったり、汚れや傷があったりした場合は、すぐにレンタルショップに連絡して交換してもらう必要があります。
葬儀会場や葬儀社によっては、提携しているレンタルサービスを紹介してくれる場合もありますので、相談してみるのも良いでしょう。
レンタルの利用を検討する際は、費用だけでなく、利便性や確実性も考慮して判断することが大切です。
まとめ
葬儀に参列する際の服装である「喪服」について、男性のブラックスーツ、女性のブラックフォーマルを中心に、選び方やマナー、そして準備方法について解説しました。
準喪服が最も一般的で失礼のない服装であり、漆黒の無地で光沢のない生地、控えめなデザインが基本であることをご理解いただけたかと思います。
急な訃報や家族葬、平服指定の場合など、状況に応じて略喪服やダークカラーのスーツで代用することも可能ですが、その際も派手な色や柄、光沢は避け、全体を地味で落ち着いた印象にまとめることが大切です。
また、スーツ本体だけでなく、ネクタイ、シャツ、靴、バッグ、アクセサリー、メイク、ヘアスタイルといった小物や身だしなみにも気を配ることで、より丁寧な弔意を示すことができます。
喪服を準備する方法としては、購入、レンタル、代用といった選択肢があり、それぞれにメリット・デメリットがありますので、ご自身の状況に合わせて最適な方法を選んでください。
最も重要なのは、故人様を偲び、ご遺族に寄り添う気持ちです。
服装は、その気持ちを表すための一つの手段に過ぎません。
しかし、適切な服装で参列することは、故人様やご遺族への敬意を示す上で非常に大切なマナーです。
この情報が、皆様が安心して葬儀に参列するための一助となれば幸いです。