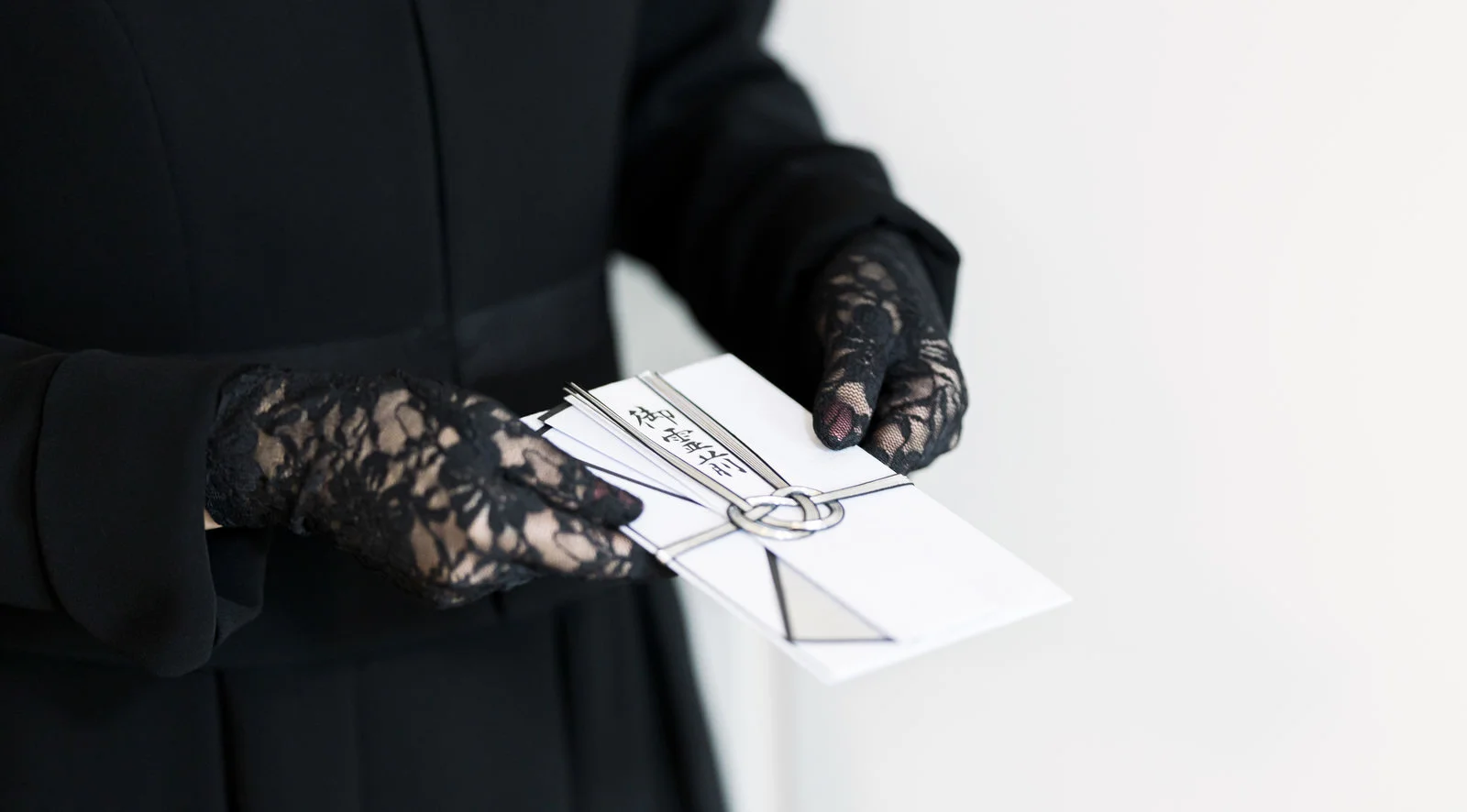故人の霊前で身だしなみを整えることは、弔意を示す上で非常に大切なことです。
特に男性が着用するスーツにおいて、ボタンの扱い一つにもマナーがあることをご存知でしょうか。
「葬式でスーツのボタンはどうする?」という疑問をお持ちの方は多いかもしれません。
葬儀という厳粛な場にふさわしい装いをするためにも、正しいボタンの留め方や、その背景にある理由を知っておくことは、失礼のない振る舞いにつながります。
ここでは、葬式におけるスーツのボタンに関する基本的なマナーから、知っておきたいポイントまで、分かりやすく丁寧にご説明します。
大切な故人を見送る場で、安心して弔意を示せるよう、ぜひ参考にしてください。
葬式でのスーツのボタンの基本マナー
葬式というフォーマルな場では、普段のビジネスシーンとは異なるマナーが存在します。
スーツのボタンの留め方もその一つです。
特に男性のスーツにおいて、ボタンの開閉は着こなしの基本でありながら、葬儀のような厳粛な場面では特に注意が必要です。
間違ったボタンの留め方は、だらしない印象を与えたり、マナーを知らないと思われたりする可能性もゼロではありません。
しかし、ご安心ください。
基本的なルールはそれほど難しくありません。
重要なのは、葬儀にふさわしい落ち着きと品格を保つことです。
一般的に、スーツのボタンはすべて留めるのが最もフォーマルな着こなしとされていますが、スーツの種類によってその常識は少し異なります。
シングルスーツとダブルスーツでは、ボタンの扱い方が違うため、ご自身の着用するスーツの種類を事前に確認しておくことが大切です。
特に初めて葬儀に参列される方や、久しぶりに礼服を着用する方は、この基本からしっかりと押さえておくことをお勧めします。
シングルスーツの場合の正しいボタンの留め方
シングルスーツは、ビジネスシーンでも最も一般的に着用されるスーツですが、葬儀のような弔事においても基本となるスタイルです。
シングルスーツには、ボタンが2つ、3つ、あるいは段返り3つといった種類があります。
それぞれのボタン数によって、留め方の基本ルールが決まっています。
まず、最も一般的な2つボタンのシングルスーツの場合、一番上のボタンのみを留めるのが正しいマナーです。
一番下のボタンは、座る時も立つ時も常に開けておくのが基本とされています。
これは、スーツのシルエットを美しく見せ、動きやすさを考慮したデザイン上の理由からきています。
次に、3つボタンのシングルスーツの場合です。
この場合は、一番上のボタンと真ん中のボタンの二つを留めるのが基本です。
一番下のボタンは、2つボタンの場合と同様に開けておきます。
そして、少し特殊な段返り3つボタンのスーツの場合、これは一番上のボタンがラペル(襟)の返り線に隠れるようにデザインされています。
この場合は、真ん中のボタンのみを留めるのが正しい留め方です。
一番上は留めずに、一番下も開けておきます。
ただし、葬儀のような厳粛な場では、すべてのボタンを留めることが最もフォーマルであるという考え方もあります。
これは、昔からの礼装の慣習に由来するもので、特に格式を重んじる場面では選択肢の一つとして考えられます。
しかし、現代においては、上記の「一番下のボタンは開ける」という着こなしが一般的であり、失礼にあたることはまずありません。
むしろ、無理にすべてのボタンを留めてスーツに不自然なシワが寄ったり、窮屈そうに見えたりする方が、かえって落ち着きのない印象を与えかねません。
葬儀では、故人への敬意と遺族への配慮が第一です。
派手な着こなしをする必要はありませんので、基本に忠実に、清潔感のある装いを心がけましょう。
ダブルスーツの場合の正しいボタンの留め方
ダブルスーツは、シングルスーツに比べてよりフォーマルな印象を与えるスーツです。
ボタンが二列に並んでおり、前合わせが深くなっているのが特徴です。
ダブルスーツのボタンの数は、一般的に4つボタンや6つボタンなどがあります。
シングルスーツとは異なり、ダブルスーツにおけるボタンの留め方には明確な基本ルールがあります。
それは、一番下のボタンを含め、内側のボタン(留め具)も含めてすべてのボタンを留めるのが正しいマナーとされている点です。
ダブルスーツは、すべてのボタンを留めることで初めてその美しいシルエットが完成するようにデザインされています。
したがって、一番下のボタンを開けてしまうと、スーツの形が崩れてしまい、だらしない印象を与えてしまいます。
これは、シングルスーツの一番下のボタンを開ける理由とは逆の考え方に基づいています。
ダブルスーツは、もともと軍服や礼服に由来するスタイルであり、きっちりと着こなすことが求められます。
特に葬儀のようなフォーマルな場では、ダブルスーツを着用する場合は、座っている時も立っている時も、すべてのボタンをしっかりと留めておくことが重要です。
内側のボタン(留め具)も忘れずに留めましょう。
この内側のボタンは、前合わせがずれるのを防ぎ、常に整った状態を保つためのものです。
ダブルスーツは、シングルスーツよりも格が高いと見なされることもあり、特に親族など、よりフォーマルな装いが求められる場合に選ばれることがあります。
しかし、最近ではビジネスシーンでも着用されるようになり、必ずしも親族だけが着用するわけではありません。
ダブルスーツを着用する際は、その独特のボタンマナーをしっかりと理解し、適切に着こなすことで、故人と遺族への敬意を示すことができます。
なぜそうするの?ボタンマナーの理由
スーツのボタンマナーには、それぞれに理由があります。
単なる形式ではなく、機能性や歴史的な背景に基づいています。
シングルスーツの一番下のボタンを開ける慣習は、「アンボタンマナー」と呼ばれ、その起源には諸説あります。
有名な説の一つは、イギリス国王エドワード7世が、太り気味だったためベストの一番下のボタンを留められず、それに倣って臣民も一番下のボタンを開けるようになったというものです。
また、乗馬をする際に動きやすくするため、あるいは初期のスーツのデザインが現在のものと異なり、一番下のボタンを留めるとシルエットが崩れたため、といった説もあります。
いずれにしても、現代のシングルスーツは、一番下のボタンを開けることを前提としたデザインになっており、開けることでウエスト周りがすっきり見え、全体のバランスが良くなるように作られています。
無理に留めると、生地に余計なシワが寄ったり、窮屈に感じたりすることがあります。
つまり、シングルスーツの一番下のボタンを開けるのは、単なる流行ではなく、現代のスーツの構造に基づいた、最も美しい着こなし方だからなのです。
一方、ダブルスーツの場合は、前述の通り、全てのボタンを留めることで初めてその完成されたシルエットが生まれます。
ダブルスーツは、シングルスーツよりも重厚感があり、きちんと感を出すために設計されています。
全てのボタンを留めることで、前合わせがしっかりと固定され、崩れることなく美しいラインを保つことができます。
また、葬儀のようなフォーマルな場では、身だしなみをきちんと整えることが故人への敬意とされます。
ボタンを全て留めることで、だらしない印象を避け、引き締まった印象を与えることができます。
これらのボタンマナーは、単に見た目を整えるだけでなく、スーツが持つ歴史や機能性を理解し、場面にふさわしい敬意を示すための重要な要素と言えるでしょう。
男性・女性・年代別に見るボタンマナーの注意点
葬儀におけるスーツのボタンマナーは、主に男性のスーツに関するものです。
しかし、女性のスーツや、参列者の年代によっても、意識すべきポイントや選択肢は異なります。
男性のスーツマナーが基本となりますが、女性や若い世代、あるいは年配の方々が葬儀に参列する際に、ボタンに関してどのような点に注意すれば良いのか、また、ボタンマナー以外にも考慮すべき身だしなみのポイントは何なのかを理解しておくことは、失礼なく弔意を示す上で非常に役立ちます。
特に、近年では服装のマナーも多様化しつつありますが、葬儀という場においては、伝統的なマナーを尊重することが依然として重要視されています。
一方で、急な訃報など、状況によっては手持ちの服で対応せざるを得ない場合もあります。
そのような状況下でも、故人への敬意を最大限に示すための工夫や考え方を知っておくことは、いざという時に慌てずに済む助けとなります。
ここでは、性別や年代、そして葬儀の場面に応じたボタンマナーや、それに付随する身だしなみの注意点について詳しく掘り下げていきます。
男性スーツと女性スーツのボタンマナーの違い
スーツのボタンマナーとして一般的に語られるのは、主に男性のスーツに関するものです。
男性のスーツには、シングルブレストとダブルブレストがあり、それぞれに明確なボタンの留め方のルールが存在します。
これは、男性スーツの構造や歴史的な背景に基づいています。
一方、女性のスーツは、男性のスーツほど厳格なボタンの留め方のルールはありません。
女性のスーツはデザインのバリエーションが豊富であり、ボタンの数や配置も多岐にわたります。
しかし、葬儀という場においては、女性も男性と同様に、落ち着いた印象を与えるように心がけることが重要です。
女性のジャケットの場合、基本的にすべてのボタンを留めるのが最もフォーマルで整った印象を与えます。
特に、ワンピースやスカートの上にジャケットを羽織るスタイルでは、ジャケットのボタンを留めることで、きちんと感がより一層増します。
ただし、デザインによってはボタンを開けて着用することを前提としているものもあります。
その場合でも、葬儀の場では、できるだけボタンを留めるか、あるいは前を閉じて着用できるデザインを選ぶのが無難です。
ボタンを開けっぱなしにしてしまうと、だらしない印象を与えかねません。
また、女性のスーツは、男性のスーツに比べてウエストがシェイプされているデザインが多く、ボタンを留めることで女性らしい美しいシルエットが生まれます。
葬儀の場においては、華美な装いは避け、シンプルで落ち着いたデザインのスーツを選び、ボタンをきちんと留めて着用することで、故人への敬意と慎みを表現することができます。
男性と女性でスーツの構造やデザインが異なるため、ボタンマナーも異なりますが、どちらの場合も「きちんと感を出す」という目的は共通しています。
若い世代と年配世代で意識すべきポイント
葬儀における服装マナーは、基本的な部分は変わりませんが、参列者の年代によって少し意識すべきポイントが異なる場合があります。
若い世代、特に20代や30代の方は、社会経験がまだ浅く、葬儀に参列する機会も少ないかもしれません。
そのため、マナーに自信がないと感じる方もいるでしょう。
若い世代が葬儀に参列する際は、基本的なボタンマナーをしっかりと守ることが最も重要です。
シングルスーツであれば一番下のボタンを開ける(または段返りなら真ん中だけ留める)、ダブルスーツなら全て留める、といった基本ルールを正確に理解し、実践することで、失礼のない装いができます。
また、若い方は体型にフィットしたスーツを着ていることが多いため、無理に全てのボタンを留めようとして窮屈に見えたり、シワが寄ったりしないように注意が必要です。
清潔感があり、体に合ったサイズの礼服を着用することが、何よりも大切です。
一方、年配世代の方は、葬儀に参列する機会も多く、マナーにも慣れている方が多いかもしれません。
年配の方の場合、伝統的なマナーをより重んじる傾向が見られることもあります。
例えば、シングルスーツでも全てのボタンを留める着こなしを選ぶ方もいらっしゃいます。
これは、昔からの礼装の考え方に基づいたものであり、間違いではありません。
ただし、現代的な視点から見ると、一番下のボタンを開けるのが一般的であるため、どちらを選んでも問題ありませんが、ご自身の年齢や立場、葬儀の雰囲気などを考慮して判断すると良いでしょう。
また、年配の方は、体型の変化に合わせてスーツがきつく感じられることもあります。
無理にボタンを留めようとせず、ゆったりとした着心地の礼服を選ぶことも、長時間にわたる葬儀を快適に過ごすために重要です。
どの世代にも共通するのは、故人への哀悼の意を示す場であるということを忘れず、華美な装いは避けるということです。
ボタンマナーも含め、全体の身だしなみで落ち着きと丁寧さを表現することが求められます。
葬儀の場面ごとのボタンマナー(通夜・告別式)
葬儀は、一般的に通夜と告別式という二つの儀式から構成されます。
どちらも故人を偲び、弔意を示す場ですが、服装マナーにおいて、通夜は急な訃報に対応するため、やや略式でも許容される傾向があります。
しかし、告別式はより正式な儀式と位置づけられるため、よりフォーマルな装いが求められます。
スーツのボタンマナーに関しても、基本的には通夜と告別式で大きな違いはありません。
どちらの場面でも、男性はシングルスーツなら一番下のボタンを開け、ダブルスーツなら全てのボタンを留める、というのが現代における一般的なマナーです。
女性も同様に、ジャケットのボタンは全て留めるか、きちんと前を閉じて着用するのが望ましいです。
しかし、通夜に急いで駆けつける場合など、手持ちのビジネススーツ(ブラックスーツ以外)で参列せざるを得ない状況も考えられます。
その場合でも、スーツのボタンマナーは礼服と同様に守るように心がけましょう。
例えば、ビジネススーツのシングル2つボタンなら、一番上のボタンだけを留めます。
また、通夜では、喪服ではなくてもダークカラーのスーツであれば許容されることがありますが、告別式では原則としてブラックスーツ(礼服)を着用するのがマナーとされています。
したがって、ボタンマナー自体は場面で変わるわけではありませんが、着用するスーツの種類(礼服か、ダークカラーのビジネススーツか)によって、全体のフォーマル度が異なるため、それに合わせた着こなしを意識する必要があります。
特に、告別式では、より正式な装いが求められるため、ボタンマナーはもちろんのこと、ネクタイや靴、靴下なども含め、全身のコーディネートに気を配ることが重要です。
通夜は夜に行われることが多く、告別式は昼に行われることが多いですが、ボタンの留め方自体が時間帯によって変わることはありません。
どちらの場面でも、故人への敬意を第一に考え、失礼のないよう、基本的なボタンマナーを守って参列しましょう。
葬式スーツ全般の身だしなみとボタン以外の注意点
葬儀に参列する際の身だしなみは、ボタンの留め方だけでなく、スーツそのものの選び方から、合わせるシャツ、ネクタイ、靴、靴下、そしてコートに至るまで、全身にわたって配慮が必要です。
これらの要素全てが組み合わさって、故人への敬意と遺族への配慮を示す装いが完成します。
ボタンマナーはスーツの着こなしの基本ですが、それ以外の部分にも気を配ることで、より一層丁寧な印象を与えることができます。
例えば、スーツの色や素材、シャツの色柄、ネクタイの選び方、靴や靴下の色など、それぞれに葬儀にふさわしいマナーがあります。
また、急な訃報で礼服を用意できない場合や、手持ちのスーツで対応する場合など、状況に応じた適切な判断も求められます。
葬儀という特別な場では、普段のビジネスシーンとは異なるマナーが求められるため、事前にこれらの知識を持っておくことは非常に重要です。
ここでは、葬式にふさわしいスーツの種類から、ボタン以外の身だしなみのチェック項目、そして急な訃報への対応やよくある疑問について掘り下げ、葬儀に安心して参列するための総合的な情報を提供します。
葬式にふさわしいスーツの種類とボタン以外のチェック項目
葬式に参列する際に最もふさわしいとされるスーツは、男性の場合はブラックスーツ(礼服)です。
これは、光沢のない深い黒色の生地で仕立てられたスーツで、弔事用の礼服として広く用いられています。
ビジネススーツの黒とは異なり、より深い黒色であることが特徴です。
このブラックスーツを着用する際は、前述のボタンマナー(シングルなら一番下を開ける、ダブルなら全て留める)を守ります。
女性の場合も、黒のスーツやアンサンブル、ワンピースなどが一般的です。
女性のスーツのボタンについては、デザインにもよりますが、基本的に全て留めるか、前を閉じて着用できるデザインを選ぶのが無難です。
ボタン以外のチェック項目としては、まずシャツの色と柄です。
男性の場合、白無地のレギュラーカラーのシャツが基本です。
ボタンダウンシャツはカジュアルな印象を与えるため、葬儀には不向きとされています。
女性の場合も、白や淡い色のブラウスを選び、フリルや飾りの少ないシンプルなものが良いでしょう。
次にネクタイです。
男性は黒無地のネクタイを着用します。
光沢のある素材や柄物は避けます。
ネクタイピンも基本的に着用しません。
女性はネックレスなどのアクセサリーは控えめにし、パールのものなどが許容されますが、派手なものは避けます。
靴は、男女ともに黒色の革靴が基本です。
男性は紐で結ぶタイプの内羽根式のストレートチップなどが最もフォーマルとされます。
エナメル素材や金具の多いものは避けます。
女性は黒色のパンプスで、ヒールが高すぎないものを選びます。
ミュールやサンダルは不適切です。
靴下は、男性は黒無地の靴下を着用します。
白い靴下や柄物は避けます。
コートを着用する場合は、黒や濃紺、グレーなどの地味な色のコートを選びます。
明るい色や派手な柄のコートは避けます。
素材も、カシミヤなどの光沢のあるものは避けるのが無難です。
これらのボタン以外のチェック項目も併せて確認することで、葬儀にふさわしい丁寧な身だしなみを整えることができます。
急な訃報への対応と手持ちのスーツでのボタンの考え方
突然の訃報に接し、急いで駆けつけなければならない場合、必ずしも礼服を用意できるとは限りません。
そのような状況では、手持ちのビジネススーツで参列することも許容される場合があります。
特に通夜においては、略装でも失礼にあたらないという考え方があります。
手持ちのスーツで対応する場合、最も無難なのはブラックスーツ以外のダークカラーのスーツです。
紺や濃いグレーのスーツであれば、落ち着いた印象を与えることができます。
この場合でも、スーツのボタンマナーは礼服と同様に守るように心がけましょう。
シングルスーツであれば一番下のボタンを開け、ダブルスーツであれば全てのボタンを留めます。
色はダークカラーでも、ボタンの留め方でだらしない印象を与えてしまっては意味がありません。
また、ビジネススーツを着用する場合でも、合わせるシャツやネクタイ、靴、靴下などは、礼服の場合と同様に、白無地のシャツ、黒無地のネクタイ、黒色の靴、黒無地の靴下を選び、葬儀にふさわしい落ち着いた装いを心がけることが重要です。
派手な色のシャツや柄物のネクタイ、明るい色の靴下などは、ビジネスシーンでは問題なくても、葬儀の場では不適切です。
一次情報として、多くの葬儀関係者やマナー講師は、「急な場合はダークカラーのビジネススーツでも仕方ないが、せめてシャツ、ネクタイ、靴下、靴は弔事用に整えるべき」とアドバイスしています。
特に、靴下は座った時に意外と目につくため、黒無地のものを選ぶように注意が必要です。
また、光沢のある生地やデザイン性の高いスーツは避け、できるだけシンプルで地味なものを選びましょう。
時間に余裕がある場合は、レンタル礼服を利用するのも一つの方法です。
しかし、時間がない場合は、手持ちのダークカラーのスーツを最大限に葬儀にふさわしい装いに近づける努力が必要です。
ボタンマナーはその基本であり、急な場合でもボタンの留め方だけは意識することで、最低限の礼儀を示すことができます。
葬式でのボタンに関するよくある疑問と一次情報からのアドバイス
葬式におけるスーツのボタンマナーについて、参列者の方々からよく寄せられる疑問がいくつかあります。
「座る時はボタンを開けても良いか?」「女性のスーツのボタンは?」「子供の制服のボタンは?」などです。
これらの疑問に対し、一般的なマナーと、葬儀の現場での実際の対応、そして一次情報に基づいたアドバイスをさせていただきます。
まず、「座る時はボタンを開けても良いか?」という疑問ですが、男性のシングルスーツの一番下のボタンは、立つ時も座る時も常に開けておくのが基本です。
それ以外のボタン(シングルスーツの一番上や真ん中、ダブルスーツの全てのボタン)は、座る時も留めておくのが正式なマナーとされています。
特にダブルスーツは、座る時に全てのボタンを留めておくことで、シルエットが崩れず、きっちりとした印象を保つことができます。
次に、「女性のスーツのボタンは?」という疑問ですが、前述の通り、女性のスーツには男性ほど厳格なルールはありませんが、葬儀という場においては、基本的に全てのボタンを留めるか、前を閉じて着用するのが最も丁寧な印象を与えます。
デザインによっては開けて着る前提のものもありますが、葬儀ではきちんと感を出すことが優先されます。
一次情報として、ある葬儀社の方に伺った話では、「最近は女性の喪服も多様化していますが、やはりジャケットのボタンはきちんと留めている方が、より丁寧に見えますね。
特に親族の方は、きっちりされている方が多い印象です」とのことでした。
最後に、「子供の制服のボタンは?」という疑問です。
学生服や制服で参列する場合、学校の規定や一般的な制服の着こなし方(ブレザーなら前ボタンを留めるなど)に従うのが基本です。
特に細かいボタンマナーを気にする必要はありませんが、だらしなく見えないよう、きちんと着こなすことが大切です。
一次情報として、地域の葬儀に詳しい方に話を伺ったところ、「昔から、子供は制服で参列するのが一般的でした。
制服の場合は、学校のルール通りに着ていれば問題ありません。
それよりも、靴や靴下、髪型など、清潔感のある身だしなみの方が重要視されますね」とのことでした。
これらの疑問に対するアドバイスは、あくまで一般的なマナーと現場での慣習に基づいたものです。
最も重要なのは、故人への弔意と遺族への配慮の気持ちであり、その気持ちを表すための身だしなみであることを忘れないようにしましょう。
まとめ
葬式におけるスーツのボタンマナーは、故人への敬意と遺族への配慮を示すための重要な要素です。
男性のシングルスーツでは一番下のボタンを開けるのが一般的であり、ダブルスーツでは全てのボタンを留めるのが正しい着こなし方です。
これらのマナーは、スーツの機能性や歴史的な背景に基づいています。
女性のスーツには男性ほど厳格なルールはありませんが、葬儀ではボタンを全て留めるか、前を閉じて着用することで、きちんと感を出すことが大切です。
また、若い世代も年配世代も、基本的なボタンマナーを守り、清潔感のある装いを心がけることが重要です。
通夜や告別式といった葬儀の場面によるボタンマナーの大きな違いはありませんが、着用するスーツの種類(礼服か、ダークカラーのビジネススーツか)によって、全体のフォーマル度が異なるため注意が必要です。
急な訃報で礼服を用意できない場合でも、手持ちのダークカラーのスーツを最大限に葬儀にふさわしい装いに近づける努力が求められます。
ボタンマナーだけでなく、シャツ、ネクタイ、靴、靴下、コートなども含め、全身の身だしなみに気を配ることで、より一層丁寧な印象を与えることができます。
葬儀という厳粛な場では、形式にこだわりすぎるよりも、故人を偲ぶ気持ちを大切にすることが最も重要ですが、マナーを守ることはその気持ちを表す一つの形です。
ここでご紹介したボタンマナーや身だしなみのポイントを参考に、故人を弔う大切な時間に安心して臨んでいただければ幸いです。