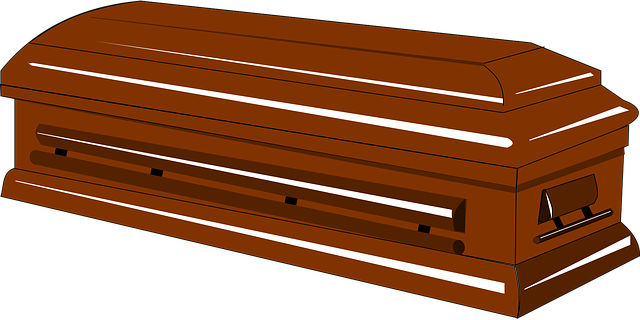ご家族やご親族、大切な方がお亡くなりになった際、弔いの気持ちを表すために参列する葬儀。
様々な準備に追われる中で、ご自身の服装について悩まれる方も少なくありません。
特に女性の場合、洋装のブラックフォーマルが一般的ですが、着物での参列を考える方もいらっしゃるでしょう。
着物には日本の伝統的な弔事における装いとしての意味合いがあり、故人や遺族への深い敬意を示すことができます。
しかし、普段着慣れない着物で、しかも弔事という特別な場となると、どのような着物を選べば良いのか、どのようなマナーがあるのか、不安に感じることが多いものです。
この記事では、「葬儀服装女性着物選び方とマナー」と題し、葬儀にふさわしい着物の種類から、必要な小物、着こなしのマナー、そして季節や状況に合わせた選び方まで、分かりやすく丁寧にご説明します。
これを読めば、安心して着物で葬儀に参列するための知識が身につくはずです。
葬儀に女性が着物で参列する際の基本
葬儀という厳粛な場にふさわしい服装として、女性が着物を選ぶことは、故人への深い哀悼の意を表すとともに、遺族への敬意を示す大変丁寧な装いとされています。
しかし、一口に着物と言っても、様々な種類や格があり、弔事に適したものが決まっています。
ここでは、まず葬儀に参列する際に知っておくべき、喪服としての着物の種類や格、そして洋装との違いといった基本的な点について詳しく解説します。
どのような立場で参列するのかによっても適切な装いは変わってきますので、ぜひ参考にしてください。
喪服としての着物の種類と格
弔事で着用する着物は「喪服」と呼ばれ、その中でも最も格式が高いのが「黒喪服(くろもふく)」です。
黒喪服は、無地の黒い生地で作られ、染め抜きの紋が入っているのが特徴です。
この紋の数によって着物の格が決まります。
最も格が高いのは「五つ紋(いつつもん)」で、背中の中央、両袖の後ろ、両胸の合計五箇所に紋が入ります。
これは正喪服(せいもふく)にあたり、主に喪主や三親等以内の親族が着用する最も正式な装いです。
次に格が高いのが「三つ紋(みつもん)」で、背中の中央と両袖の後ろの三箇所に紋が入ります。
そして、最も格が低いのが「一つ紋(ひとつもん)」で、背中の中央一箇所にのみ紋が入ります。
三つ紋や一つ紋の黒喪服は、準喪服(じゅんもふく)にあたり、親族や故人と特に親しかった方が着用することが多いです。
また、黒喪服以外にも「色喪服(いろもふく)」というものがあります。
これは、黒以外の地味な色(紫、緑、紺、灰色など)の無地の着物で、一つ紋または三つ紋が入っているものです。
色喪服は、親族以外の方が通夜や葬儀に参列する場合や、法事などで着用されることがありますが、葬儀においては黒喪服が最も一般的かつ正式な装いとされています。
特に近親者の葬儀では、黒喪服を選ぶのが基本です。
準喪服・正喪服の選び分け方
葬儀における着物の選び分けは、ご自身の故人との関係性によって決まります。
最も格の高い「正喪服」である黒喪服の五つ紋は、主に喪主とその配偶者、そして故人の三親等以内の親族が着用します。
これは、喪家として弔いの気持ちを最も重く表す立場であるためです。
一方、「準喪服」にあたる黒喪服の三つ紋や一つ紋、あるいは色喪服の一つ紋・三つ紋は、それ以外の親族や、故人と生前親しかった友人などが着用します。
一般の参列者として葬儀に赴く場合は、準喪服である黒喪服の一つ紋や三つ紋を選ぶのが一般的です。
ただし、最近では家族葬など形式が多様化しており、親族間でも洋装のブラックフォーマルを選ぶケースが増えています。
しかし、伝統的な葬儀や、格式を重んじるご家庭においては、親族が着物を着用することが多いです。
ご自身の立場と、参列する葬儀の形式、そして可能であれば事前に遺族の意向を確認することが、適切な喪服を選ぶ上で非常に重要になります。
迷った場合は、ご自身の立場よりも少し控えめな格の着物を選ぶ方が、失礼にあたる可能性が低くなります。
洋装とのマナーの違い
葬儀の服装として、着物と洋装(ブラックフォーマル)はどちらも正式な喪服とされていますが、それぞれに特有のマナーがあります。
洋装の場合、シンプルで露出の少ない黒のワンピースやアンサンブルが基本で、アクセサリーなども控えめにします。
一方、着物の場合、選ぶべき着物の種類や小物が細かく定められており、着こなしにも独特のルールがあります。
例えば、洋装では黒のストッキングを着用しますが、着物では白い足袋を履きます。
また、洋装では手袋を着用することがありますが、着物では原則として着用しません。
最も大きな違いは、着物の方が格が高く、より丁寧な弔意を示す装いとされている点です。
洋装は現代の一般的な喪服として広く受け入れられていますが、着物は日本の伝統文化に根差した装いであり、格式を重んじる場や、遺族が着物を着用する場合などに選ばれることが多いです。
どちらを選ぶにしても、故人を偲び、遺族に寄り添う気持ちが最も大切です。
ご自身の立場や状況、そして周囲との調和を考慮して、適切な服装を選ぶようにしましょう。
最近では、親族の中でも着物を着用する人が減ってきているため、事前に他の親族の服装を確認しておくと安心です。
葬儀用着物に必要な小物と着こなしのマナー
葬儀にふさわしい着物を選んだら、次に重要になるのが、それに合わせる小物です。
喪服の着物は、着物本体だけでなく、帯や帯揚げ、帯締め、長襦袢、草履、バッグなど、合わせる小物にも厳格なマナーがあります。
これらの小物を間違えてしまうと、せっかく適切な格の着物を選んでも、全体の装いとして不適切になってしまう可能性があります。
ここでは、葬儀用着物に合わせるべき小物の選び方と、着こなしに関するマナーについて詳しく解説します。
細部まで気を配ることで、故人や遺族に失礼のない、心遣いの行き届いた装いを完成させることができます。
帯や帯揚げ・帯締めなどの選び方
喪服の着物に合わせる帯は、「黒共帯(くろともおび)」と呼ばれる、黒一色の帯を選びます。
黒共帯には、染め帯と織り帯がありますが、喪服には光沢がなく、地味な柄や無地の染め帯が最もふさわしいとされています。
織り帯は光沢があり、華やかな印象を与えるため、弔事には向きません。
帯の柄は、おめでたい柄や派手な柄は絶対に避け、無地か、蓮や雲、流水など、控えめで弔事にふさわしい柄を選ぶのがマナーです。
次に、帯揚げと帯締めですが、これらも黒無地のものを選びます。
帯揚げはちりめんなどの光沢のない素材で、黒一色のものを使用します。
帯締めは、平組や丸組の黒無地のものを選び、房は目立たないように内側に入れるのが一般的です。
色喪服を着用する場合は、帯や帯揚げ、帯締めも黒無地で揃えるのが基本ですが、地域や宗派によっては、地味な色の帯や小物を用いる場合もあります。
しかし、最も間違いがないのは黒無地で統一することです。
帯結びは、お太鼓結びなど、シンプルで落ち着いた結び方を選びます。
変わり結びや華やかな結び方は、慶事の際に用いるものなので、弔事では避けてください。
長襦袢や足袋、草履・バッグの注意点
喪服の着物の下に着る長襦袢は、白無地のものを選びます。
素材は絹やポリエステルなどがありますが、色は必ず白で、柄のないものを選んでください。
半襟も、白無地のものを使用します。
刺繍や柄が入った半襟は、おしゃれ着や慶事の際に用いるものなので、弔事には不適切です。
足袋は、これも必ず白足袋を着用します。
黒足袋や色足袋は、おしゃれ足袋として扱われるため、弔事には向きません。
また、柄足袋やレース足袋なども避けてください。
草履は、黒色の布製で、光沢のないものを選びます。
エナメルやパテントレザーなど、光沢のある素材は慶事の際に用いるものなので、弔事には不適切です。
草履の鼻緒も、黒無地のものが基本です。
バッグも同様に、黒色の布製で、光沢のないものを選びます。
金具が目立つものや、装飾が多いもの、ブランドロゴが大きく入ったものなども避けるべきです。
小さめの手提げタイプや、クラッチバッグタイプなど、シンプルで必要なもの(袱紗、数珠、ハンカツなど)が入る程度の大きさが良いでしょう。
これらの小物は、着物本体と同様に、派手さや華やかさを一切排除し、控えめで地味なものを選ぶことが、弔事における最も重要なマナーです。
髪型とアクセサリーのタブー
葬儀に参列する際の髪型も、落ち着いた印象を与えることが大切です。
長い髪は、清潔感を保つためにも一つにまとめます。
まとめる位置は、耳より下の低い位置が良いでしょう。
お団子にする場合も、頭の高い位置ではなく、低い位置でコンパクトにまとめます。
前髪は、顔にかからないようにすっきりとさせます。
ショートヘアの場合も、乱れないように整えます。
全体的に、派手なアレンジや逆毛、ボリュームを出しすぎるスタイルは避けるべきです。
髪飾りは、原則として付けません。
どうしても必要な場合は、黒色で光沢のないシンプルなピンやゴムを使用する程度に留めます。
アクセサリーについても、慶事の際に用いるような華やかなものは一切身につけません。
結婚指輪はつけていても構いませんが、それ以外の指輪やイヤリング、ピアス、ネックレスなどは原則として外します。
ただし、パールのネックレスについては、一連のものであれば許容される場合があります。
これは、涙の象徴として弔事にふさわしいとされる考え方があるためです。
しかし、二連や三連のパールネックレスは「不幸が重なる」という意味合いに繋がるため、絶対に避けてください。
また、化粧も薄く、ナチュラルメイクを心がけます。
口紅の色も控えめにし、濃い色やラメ入りのものは避けます。
香水も、強い香りのものは周囲の方に配慮し、つけないのがマナーです。
季節や状況に合わせた着物選びと準備
葬儀に参列する時期によって、適切な着物や小物は変わってきます。
特に日本の四季は明確であり、夏場と冬場では着物の素材や重ね方、防寒・暑さ対策が重要になります。
また、着物を着用するとなると、洋装よりも準備に手間がかかります。
ご自身で着付けができない場合は、着付けの依頼も必要になりますし、着物自体を用意する方法も、購入とレンタルの選択肢があります。
ここでは、季節に合わせた着物選びのポイントや、レンタルと購入のメリット・デメリット、そして着付けや事前の準備について詳しく解説します。
慌てずに準備を進めることで、心穏やかに故人を送ることができます。
夏場・冬場の着物と小物
夏場(一般的に6月~9月頃)の葬儀では、暑さ対策として「薄物(うすもの)」と呼ばれる透け感のある着物を着用します。
喪服の場合、絽(ろ)や紗(しゃ)といった透け感のある織り方の黒無地の着物が夏用として用いられます。
長襦袢も夏用の絽や麻素材のものを選び、帯も夏用の絽や紗の黒共帯を合わせます。
暑い時期だからといって、肌が多く露出するような着こなしは避け、あくまでもフォーマルな場にふさわしい装いを心がけてください。
冬場(一般的に10月~5月頃)の葬儀では、「袷(あわせ)」と呼ばれる裏地のついた着物を着用します。
これは通常の喪服の着物です。
寒さ対策として、長襦袢の下に肌襦袢や裾よけを着たり、足袋もネル裏足袋など厚手のものを選ぶことができます。
さらに、防寒具として、黒無地のコートや羽織、ショールなどを着用しても構いません。
ただし、会場内では脱ぐのがマナーです。
手袋も黒無地のものを選び、会場に入る前に外します。
夏場も冬場も、共通して言えるのは、季節に合わせて快適に過ごせる工夫をしつつも、喪服としての格式とマナーを守ることが最も重要であるということです。
特に夏場は汗対策として、替えの肌着やハンカチなどを多めに用意しておくと安心です。
レンタルと購入、それぞれのメリット・デメリット
葬儀用の着物を用意する方法としては、大きく分けてレンタルと購入があります。
それぞれにメリットとデメリットがありますので、ご自身の状況に合わせて検討しましょう。
レンタルの最大のメリットは、費用を抑えられることと、保管や手入れの手間がかからないことです。
葬儀のたびに異なる着物や小物を借りることも可能で、流行や体型の変化にも対応しやすいです。
ただし、レンタルの場合は、予約が必要であり、特に急な訃報の場合、希望のサイズやデザインが見つかりにくい可能性があります。
また、返却期限を守る必要があります。
一方、購入のメリットは、いつでもすぐに着用できることと、ご自身の体型に合わせて仕立てられるため、着心地が良いことです。
一度購入すれば、何度でも着用でき、長期的に見ればレンタルよりも割安になる場合もあります。
しかし、購入には初期費用がかかり、また、着用後の手入れや長期保管に気を配る必要があります。
特に喪服の着物は、次にいつ着るか分からないため、湿気などによるカビを防ぐために、定期的に風通しを行うなどの手入れが欠かせません。
どちらを選ぶかは、着用する頻度や、保管スペースの有無、予算などを考慮して決めると良いでしょう。
最近では、ネットで手軽にレンタルできるサービスも増えています。
着付けと持ち物の最終チェック
着物を着用する場合、ご自身で着付けができる方以外は、着付けを誰かに依頼する必要があります。
着付けを依頼できる場所としては、美容院や呉服店、または自宅に出張してくれる着付け師などがいます。
訃報は突然訪れるものですので、着付けの予約は早めに行うことが重要です。
特に週末や友引の日などは混み合う可能性があります。
着付けを依頼する際は、喪服の着付けに慣れているか、時間や場所の融通が利くかなどを確認しておくと安心です。
また、着付けに必要な小物(肌襦袢、裾よけ、長襦袢、帯、帯揚げ、帯締め、伊達締め、腰紐、帯板、帯枕、コーリンベルト、三重仮紐、足袋、草履など)は、全て揃っているか事前に確認しておきましょう。
レンタルであれば一式セットになっていることが多いですが、購入した着物の場合はご自身で揃える必要があります。
葬儀に参列する際の持ち物も確認しておきましょう。
必須の持ち物としては、袱紗(ふくさ)に包んだ香典、数珠、そして涙を拭くための白いハンカチがあります。
その他、予備の足袋や、夏場であれば扇子などもあると便利です。
出発前に、服装全体に乱れがないか、小物は全て揃っているか、持ち物は忘れていないか、最終チェックを怠らないようにしましょう。
準備をしっかり行うことで、落ち着いて故人を見送ることに集中できます。
まとめ
葬儀に女性が着物で参列することは、故人への深い敬意と弔いの気持ちを表す、日本の伝統的な装いです。
適切な喪服の着物を選ぶためには、まずご自身の立場を理解し、正喪服にあたる黒喪服の五つ紋か、準喪服にあたる黒喪服の三つ紋や一つ紋、あるいは色喪服の中から適切なものを選ぶことが重要です。
合わせる小物も、帯は黒共帯、帯揚げ・帯締めは黒無地、長襦袢と半襟、足袋は白無地、草履とバッグは黒布製で光沢のないものを選ぶのがマナーです。
髪型はシンプルにまとめ、アクセサリーは原則として外します。
季節に合わせた着物選びや、レンタルか購入かの検討、そして着付けや持ち物の準備も、滞りなく行うことで、心穏やかに故人をお見送りできます。
着物での参列は、洋装に比べて準備に手間がかかるかもしれませんが、その分、故人や遺族への丁寧な心遣いを示すことができます。
大切なのは、形式だけでなく、故人を偲ぶ気持ちを込めて装いを選ぶことです。
マナーを守り、心を込めて準備することで、失礼なく葬儀に参列することができるでしょう。
この記事が、葬儀に着物で参列される際の不安を解消し、故人を大切に思う気持ちを伝える一助となれば幸いです。