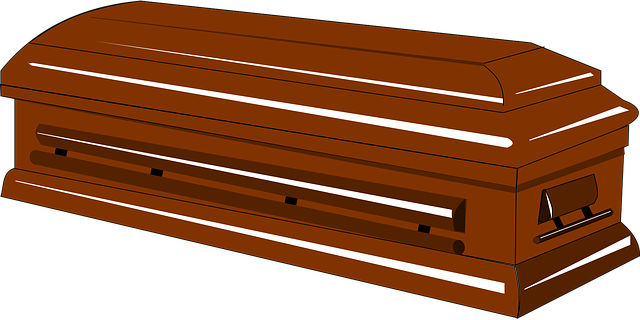大変な時期にご葬儀に参列されることになり、服装、特に上着についてどのように選べば良いのか迷われている方もいらっしゃるかもしれません。
故人を偲び、ご遺族に寄り添う気持ちを表す場において、服装は大切なマナーの一つです。
特に外気の影響を受ける上着は、季節や気候によって適切なものを選ぶ必要があります。
この記事では、葬儀にふさわしい上着の選び方とマナーについて、失礼なく参列するためのポイントを詳しく解説します。
「葬儀服装上着選び方マナー」をしっかりと理解し、安心して故人をお見送りできるよう、ぜひ最後までお読みいただければ幸いです。
葬儀の上着選び、基本のマナーとは?
葬儀に参列する際、上着は防寒や雨風をしのぐ役割だけでなく、フォーマルな装いを完成させるためにも重要なアイテムです。
しかし、普段使いのコートとは異なり、葬儀という厳粛な場にふさわしいものを選ぶ必要があります。
最も大切なのは、派手さや華やかさを避け、控えめで落ち着いた印象を与えることです。
色は黒が基本ですが、濃紺やチャコールグレーといったダークカラーでも問題ありません。
柄物は避け、無地を選ぶのが鉄則です。
素材に関しても、光沢のあるものやカジュアルすぎるものは不適切とされています。
ウールやカシミヤ、ポリエステルなどの控えめな素材を選びましょう。
また、ファーや装飾品が付いているものは取り外し、シンプルな状態にすることがマナーです。
葬儀の規模や故人との関係性によって多少の違いはありますが、一般的には「控えめに、目立たず」が原則となります。
特に親族として参列する場合は、より格式を重んじる傾向がありますので注意が必要です。
葬儀にふさわしい上着の色と素材
葬儀に参列する際の上着の色は、黒が最も一般的であり、最も無難な選択肢です。
しかし、急な弔事などで黒いコートがない場合や、地域や宗派によっては、濃紺やチャコールグレーといった極めて濃いダークカラーであれば許容されることもあります。
ただし、黒以外の色を選ぶ場合は、光の当たり方で明るく見えないか、他の参列者から見て違和感がないかなど、慎重に判断する必要があります。
不安な場合は、やはり黒を選ぶのが安心です。
素材に関しては、ウールやカシミヤ混、ポリエステル、レーヨンなどが適しています。
重要なのは、光沢が少なく、肌触りが滑らかで落ち着いた質感であることです。
たとえば、ビニール素材やレザー、スエード、デニム、コーデュロイといったカジュアルな素材や、動物の毛皮(リアルファー、フェイクファー問わず)は殺生を連想させるため、葬儀には不向きとされています。
ツイードのような織り目が目立つ素材も、カジュアルに見える場合があるため避けた方が良いでしょう。
特に冬場は防寒性の高いコートが必要になりますが、厚手のウールコートやカシミヤコートを選ぶ場合も、表面に光沢がなく、シンプルなデザインのものを選びましょう。
素材選びに迷ったら、ブラックフォーマルウェアを扱う専門店で相談するか、礼服に合わせることを前提に作られたフォーマルコートを選ぶのが確実です。
季節ごとの上着選びのポイント
葬儀は季節を問わず執り行われますので、それぞれの時期に合わせた上着選びが求められます。
冬場は、防寒対策が最も重要になります。
ウールやカシミヤ混のロングコートやハーフコートが一般的です。
色は黒、デザインはシンプルで装飾のないものを選びます。
会場内では上着を脱ぐため、厚すぎると持ち運びに困ることもあります。
外での防寒性と室内での扱いやすさのバランスを考慮して選びましょう。
春や秋といった季節の変わり目は、気温の変化に対応できる上着が便利です。
トレンチコートやステンカラーコートのような、比較的薄手のコートが適しています。
素材はポリエステルや綿混紡などで、色は黒や濃紺を選びます。
ライナー付きのものであれば、気温に合わせて調節できるため重宝します。
夏場は、基本的に上着は不要です。
しかし、冷房の効いた室内や、急な雨に備えて、薄手のジャケットやカーディガンなどを持参する人もいます。
この場合も、色は黒やダークカラーで、素材は綿や麻混紡など、通気性の良いものを選びましょう。
ただし、カジュアルに見えないよう、あくまでシンプルなデザインのものを選び、会場に入る際には脱ぐのがマナーです。
季節ごとの気候に合わせて、適切な素材と厚さの上着を選ぶことが、快適に、そしてマナーを守って参列するための鍵となります。
男性・女性別、適切な上着の種類
男性と女性では、葬儀にふさわしいとされる上着の種類が異なります。
男性の場合、最も一般的なのはブラックフォーマルスーツに合わせるコートです。
デザインとしては、チェスターコートやステンカラーコートが適しています。
色は黒または濃紺で、素材はウールやカシミヤなどの落ち着いたものを選びます。
丈は膝丈程度が一般的ですが、デザインによってはハーフ丈でも問題ありません。
カジュアルな印象を与えるダウンコートやモッズコート、ダッフルコートなどは避けるべきです。
スーツの上から羽織るため、肩周りにゆとりがあり、スーツのシルエットを崩さないサイズ感を選ぶことが重要です。
一方、女性の場合は、ブラックフォーマルウェア(ワンピースやアンサンブル、スーツなど)に合わせるフォーマルコートやシンプルなデザインのコートが適しています。
デザインとしては、テーラードカラーのコートやスタンドカラーのコートなど、襟元がすっきりとしたものが一般的です。
色は黒で、素材はウール、カシミヤ、ポリエステルなどで、光沢のないものを選びます。
丈は、スカートの裾が隠れるくらいのロング丈がよりフォーマルとされていますが、膝丈程度でも問題ありません。
カジュアルなデザインのコートや、装飾が多いコート、明るい色のコートは避けるべきです。
男女ともに、フォーマルな場にふさわしい、シンプルで控えめなデザインと色、素材の上着を選ぶことが基本となります。
葬儀会場での上着の扱い方と注意点
葬儀会場に到着してから、上着の扱い方にもいくつかのマナーがあります。
単に脱いで済ませるのではなく、いつ脱ぐか、どこに置くか、どのように持ち運ぶかなど、細やかな配慮が求められます。
会場の入り口に到着したら、建物に入る前に上着を脱ぐのが一般的です。
特に受付を通る際は、上着を脱いだ状態で臨むのがより丁寧な印象を与えます。
脱いだ上着は、裏返しにしてたたむか、腕にかけて持ち運びます。
これは、外の埃や汚れを会場内に持ち込まないため、そして弔意を表すための所作とされています。
ただし、雨や雪で濡れている場合は、軽く水気を払ってからたたむなど、周囲への配慮が必要です。
会場内では、基本的に上着は着用しません。
着席する際や焼香をする際にも、上着は脱いでおきます。
脱いだ上着の置き場所にも注意が必要です。
椅子の背もたれにかけるのは、後ろを通る方の邪魔になったり、落ちてしまう可能性があるため避けた方が無難です。
膝の上にたたんで置くか、床に置く場合は、邪魔にならないよう足元にコンパクトにたたんで置くのが良いでしょう。
これらの上着の扱いは、故人やご遺族、そして他の参列者への敬意を示す行為となります。
受付時や室内での上着の着脱マナー
葬儀会場に到着し、まず行うのが受付です。
受付では、記帳や香典のお渡しをしますので、スムーズに行えるよう建物に入る前に上着を脱いでおくのがマナーとされています。
特に冬場など厚手の上着を着用している場合は、室内に入ると暑く感じることもありますし、受付で慌てて脱ぐのは見苦しくなる可能性があります。
事前に脱いでおくことで、落ち着いて受付を済ませることができます。
脱いだ上着は、丁寧にたたんで腕にかけます。
この際、裏地を外側にする「裏返し」にたたむのが正式なマナーとされていますが、最近ではそこまで厳格ではないという考え方もあります。
しかし、外の汚れを室内に持ち込まないという意味でも、裏返してたたむのは理にかなっています。
会場内に入ったら、原則として上着は着用しません。
式の間はもちろん、控え室などでも、特別な事情(体調が悪い、極端に寒いなど)がない限りは脱いでおくのが一般的です。
会場内での移動時も、上着は着用せず、たたんで手に持って移動します。
これは、コートを着たままではカジュアルに見えたり、動きにくかったりするためです。
焼香の際も、コートは脱いだ状態で臨みます。
これらの所作は、故人への敬意と、厳粛な場にふさわしい態度を示すものです。
脱いだ上着の持ち運びと置き場所
会場内で脱いだ上着は、適切に持ち運び、邪魔にならない場所に置く必要があります。
脱いだ上着は、丁寧にたたんでコンパクトにすることが大切です。
特にロングコートの場合は、三つ折りや四つ折りにして、腕にかけたり手に持ったりしやすいようにします。
前述の通り、裏地を外側にしてたたむのが正式なマナーとされています。
会場内を移動する際は、たたんだ上着を手に持って移動します。
着席する場所に着いたら、上着を置く場所を考えます。
最も一般的なのは、膝の上にたたんで置く方法です。
特に小さな葬儀場や、参列者が多い場合で、荷物を置くスペースが限られている場合に適しています。
もう一つの方法として、足元に置くスペースがあれば、コンパクトにたたんで足元に置くことも可能です。
ただし、他の参列者の通行の邪魔にならないよう、通路にはみ出さないように注意が必要です。
避けるべき置き場所としては、椅子の背もたれにかけること、そして床に広げて置くことです。
椅子の背もたれにかけると、後ろを通る方が引っ掛けたり、焼香の際に落ちてしまうリスクがあります。
また、床に広げて置くのは、他の参列者の邪魔になるだけでなく、見た目にも美しくありません。
大規模な葬儀場では、クロークが用意されている場合もありますので、その場合はクロークを利用するのが最もスマートです。
しかし、多くの場合、自分で管理する必要がありますので、たたんで膝の上や足元に置くのが基本的な対応となります。
知っておきたい、上着に関する細かな疑問
葬儀の上着に関して、基本マナー以外にも細かな疑問がいくつかあります。
例えば、「冬場の葬儀で、コートの中に着る服は?」「雨が降っている場合、レインコートは?」「子供の上着は?」「急な弔事で適切な上着がない場合は?」といった疑問です。
冬場のコートの中に着る服は、ブラックフォーマルウェアが基本です。
防寒のためにインナーを重ね着することは問題ありませんが、コートを脱いだ際に下に着ているものが葬儀にふさわしい服装である必要があります。
雨が降っている場合、傘は黒や紺、グレーなどの地味な色を選びます。
レインコートについては、葬儀用のレインコートは一般的ではありませんが、急な雨でやむを得ない場合は、黒や紺などの地味な色で、シンプルで光沢のない素材のものを選ぶのが良いでしょう。
ただし、会場内では必ず脱ぎ、水気をよく拭き取ってからたたんで持ち運びます。
子供の上着についても、大人と同様に黒や紺、グレーなどの地味な色で、シンプルで控えめなデザインのものが望ましいです。
制服があれば制服が最もふさわしい服装となります。
急な弔事で適切な上着がない場合は、無理に購入するのではなく、濃い色の無地のコートで、装飾のないものを選び、できるだけ控えめな印象になるよう工夫します。
どうしても適切なものがない場合は、ご遺族や親しい方に相談してみるのも一つの方法です。
これらの細かな疑問についても、基本となる「控えめに、目立たず」という原則を忘れずに判断することが大切です。
葬儀の上着、どこでどう選ぶ?具体的な購入・レンタルのヒント
葬儀に参列する機会はそう頻繁にあるわけではありませんが、いざという時に慌てないためにも、適切な上着を準備しておくと安心です。
葬儀にふさわしい上着を手に入れる方法はいくつかあります。
一つは購入、もう一つはレンタルです。
それぞれにメリット・デメリットがありますので、ご自身の状況に合わせて検討しましょう。
購入する場合、ブラックフォーマルウェア専門店、百貨店のフォーマルウェア売り場、紳士服店や婦人服店、最近ではオンラインストアでも購入できます。
専門店や百貨店では、専門知識を持った店員さんに相談しながら選べるため、失敗が少なく安心です。
レンタルは、購入するよりも費用を抑えられるのがメリットです。
急な場合や、今後使う機会が少ないと考えられる場合に便利です。
レンタルサービスは、専門のレンタルショップや、オンラインのレンタルサービスを利用できます。
どちらの方法を選ぶにしても、実際に試着して、サイズ感や礼服とのバランスを確認することが非常に重要です。
フォーマル専門店から身近な店舗まで
葬儀にふさわしい上着を購入する場合、様々な選択肢があります。
最も確実なのは、ブラックフォーマルウェアを専門に扱う店舗や、百貨店のフォーマルウェア売り場です。
これらの店舗では、葬儀や法事に特化した上着が豊富に揃っており、素材やデザイン、マナーについて詳しい店員さんに相談しながら選ぶことができます。
礼服とのセットで購入できる場合もあり、全体のバランスを考えて選べるのが大きなメリットです。
次に、紳士服店や婦人服店でも、礼服やそれに合わせるコートを取り扱っている場合があります。
特に大手チェーン店などでは、比較的リーズナブルな価格で購入できることもあります。
ただし、フォーマル専門ではないため、品揃えや店員さんの知識にばらつきがある可能性もあります。
最近では、オンラインストアでもフォーマルウェアやコートを購入できます。
店舗に行く時間がない場合や、価格を比較して選びたい場合に便利です。
しかし、実際に試着できないため、サイズ選びや素材感の確認が難しいというデメリットがあります。
返品・交換が可能か、事前に確認しておくことが重要です。
身近な店舗としては、ユニクロなどの量販店でも、シンプルなデザインの黒いコートが見つかることがあります。
ただし、あくまで普段使いのコートであるため、素材の光沢やデザインがフォーマルな場にふさわしいか、慎重に見極める必要があります。
どこで購入する場合でも、必ず試着をして、礼服とのバランスやサイズ感を確認することが大切です。
失敗しないための試着と確認ポイント
葬儀の上着を選ぶ際に、失敗しないためには試着が非常に重要です。
特に礼服の上から着用することを想定して試着を行いましょう。
試着する際は、必ず礼服(スーツやワンピースなど)を着用した状態で行います。
普段着の上から試着すると、実際のサイズ感やシルエットが大きく異なってしまう可能性があります。
上着を着てみて、肩周りや袖、丈の長さが適切かを確認します。
特に冬場の厚手コートは、礼服の上にゆったりと羽織れるサイズを選ぶ必要があります。
きつすぎると動きにくく、不自然なシルエットになってしまいます。
逆に大きすぎると、だらしない印象を与えてしまいます。
デザインについては、装飾がないか、ボタンの色や形が派手でないか、襟の形がフォーマルな場にふさわしいかなどを確認します。
素材の光沢がないか、織り目が目立ちすぎないかなども、明るい場所で確認しましょう。
動きやすさも重要なポイントです。
腕を上げたり、前かがみになったりしてみて、窮屈さがないか確認します。
特に焼香などの動作をスムーズに行えるかイメージしてみましょう。
鏡で全身のバランスを確認し、礼服との相性が良いかどうかもチェックします。
バッグや靴など、他の小物とのバランスも考慮すると、より統一感のある装いになります。
これらのポイントを丁寧に確認することで、いざという時に安心して着用できる、適切な上着を選ぶことができます。
長く使える上着選びの視点
葬儀の上着は、頻繁に買い替えるものではありません。
だからこそ、長く使えるものを選ぶ視点を持つことが大切です。
長く使える上着を選ぶためには、いくつかのポイントがあります。
一つは、流行に左右されない、シンプルでベーシックなデザインを選ぶことです。
奇抜なデザインや特徴的なシルエットのものは、数年後には古く感じてしまう可能性があります。
テーラードカラーやスタンドカラーなど、定番のデザインであれば、いつの時代でも安心して着用できます。
二つ目は、高品質で丈夫な素材を選ぶことです。
ウールやカシミヤなど、天然素材は手入れが必要ですが、適切に手入れすれば長く風合いを保つことができます。
ポリエステルなどの合成繊維でも、高品質なものであれば丈夫でシワになりにくく、手入れが比較的容易です。
安価な素材は、毛玉ができやすかったり、型崩れしやすかったりすることがありますので注意が必要です。
三つ目は、手入れのしやすさも考慮することです。
クリーニングが必要な素材か、自宅で手洗いできるかなど、購入前に確認しておきましょう。
特に冬場のコートは、シーズンオフの保管方法も重要になります。
四つ目は、サイズ選びも重要です。
体型の変化に対応できるよう、少しゆとりのあるサイズを選ぶか、調整可能なデザインのものを選ぶのも一つの方法です。
これらの点を考慮して選ぶことで、一度購入すれば、今後の弔事にも対応できる、信頼できる一着として長く愛用することができるでしょう。
まとめ
葬儀に参列する際の上着選びとマナーは、故人を偲び、ご遺族に敬意を表すための大切な要素です。
上着の色は黒を基本とし、濃紺やチャコールグレーなどのダークカラーを選ぶ場合も、控えめな印象を心がけましょう。
素材は光沢のないウールやカシミヤ、ポリエステルなどが適しており、カジュアルな素材や動物の毛皮は避けるのがマナーです。
季節に合わせて、冬は防寒性の高いコート、春・秋は薄手のコート、夏は基本的に不要ですが、冷房対策に薄手の羽織り物を用意すると良いでしょう。
男性はチェスターコートやステンカラーコート、女性はフォーマルコートやシンプルなロングコートが一般的です。
会場に到着したら、建物に入る前に上着を脱ぎ、丁寧にたたんで持ち運びます。
受付や室内では上着を着用せず、着席する際は膝の上や足元に邪魔にならないように置くのがマナーです。
急な弔事で適切な上着がない場合でも、手持ちの最も控えめなコートを選び、装飾を外すなどの工夫で対応できます。
適切な上着は、ブラックフォーマル専門店や百貨店、紳士服・婦人服店などで購入できます。
レンタルという選択肢もあります。
購入・レンタルどちらの場合も、礼服の上から試着し、サイズ感やデザイン、素材をしっかり確認することが失敗しないためのポイントです。
流行に左右されないシンプルで高品質なものを選べば、長く安心して着用できます。
これらのマナーや選び方のポイントを押さえておけば、いざという時にも落ち着いて故人をお見送りできるはずです。