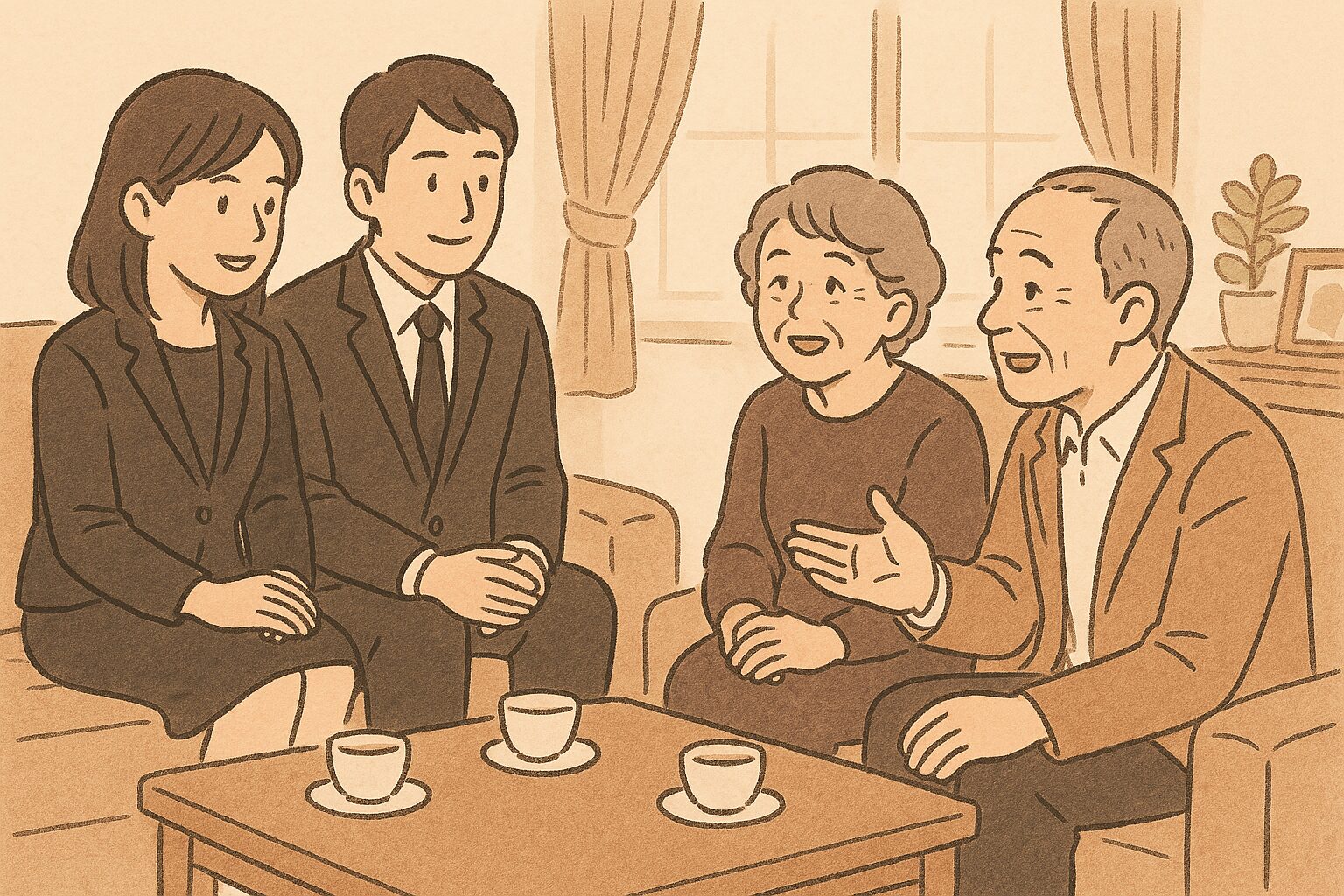大切な方を送る葬儀という場。
悲しみの中で迎えるその日、身だしなみには気を配りたいけれど、どのようなメイクがふさわしいのか、特に目元は印象を左右するため悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。
華やかなメイクは控えなければならないけれど、全くしないと顔色が悪く見えてしまう。
そんな時、自然で控えめな「葬儀メイクでのアイラインの引き方解説」を知っておくと、少しでも安心してその場に臨むことができます。
この記事では、葬儀という特別な場にふさわしいアイラインの考え方から、具体的な引き方、そして涙で崩れてしまった時の対処法まで、分かりやすく丁寧にご紹介します。
故人への敬意と遺族への配慮を大切にした、心に寄り添うメイクについて一緒に考えていきましょう。
葬儀メイクでアイラインを引く意味と基本の考え方
葬儀という場は、故人を偲び、遺族に寄り添うためのものです。
そのため、参列者も遺族も、派手な装いやメイクは避けるのが一般的なマナーとされています。
では、なぜメイクをする必要があるのでしょうか。
それは、身だしなみを整えることで、故人や遺族に対して失礼のないように、また、悲しみの場であっても最低限の社会的な礼儀を示すためです。
完全にノーメイクで顔色が悪く見えてしまうと、かえって周囲に心配をかけてしまうこともあります。
メイクは、悲しみを乗り越えようとする気持ちや、故人への敬意を表す一つの方法でもあるのです。
特に目元は、顔の中でも感情が表れやすく、また、疲労や悲しみによってくすみやクマが出やすい部分です。
アイラインは、目元を自然に引き締め、顔色を少しでも明るく見せる効果が期待できます。
しかし、使い方を間違えると、場にそぐわない派手な印象になってしまうため、最大限の配慮が必要です。
葬儀メイクにおけるアイラインの基本は、「控えめであること」「清潔感があること」「崩れにくいこと」の三つ。
目力をアップさせるためではなく、あくまでも「疲れて見えがちな目元を自然に整える」という目的意識を持つことが大切です。
自分の顔色を健康的に見せつつ、悲しみに寄り添うような穏やかな表情を保つためのサポートとしてアイラインを活用しましょう。
葬儀におけるメイクのマナーとアイラインの役割
葬儀の場でのメイクは、普段のメイクとは目的が大きく異なります。
華やかさや個性を表現するのではなく、あくまで故人への哀悼の意と、遺族への配慮を示すための身だしなみです。
そのため、色使いは最小限に抑え、落ち着いたトーンでまとめるのが基本となります。
ファンデーションで肌の色むらを整え、眉を自然に描く程度でも十分ですが、目元がぼやけてしまったり、疲れて見えたりするのを防ぐためにアイラインを取り入れる方も少なくありません。
アイラインの役割は、目を大きく見せることではなく、まぶたのたるみや目の周りのくすみを自然にカバーし、目元をすっきりと見せることにあります。
これにより、顔全体が引き締まり、悲しみの中にあっても失礼のない、きちんとした印象を与えることができます。
例えば、寝不足が続くと目の下がくすんだり、まぶたが腫れぼったくなったりすることがあります。
このような場合、細く自然なアイラインを引くことで、目元の印象が少し改善され、顔色が悪く見えるのを防ぐことができます。
重要なのは、「メイクをしている」と強く感じさせないことです。
まるで素顔の延長であるかのように、肌や目元に自然になじむように仕上げることが求められます。
アイラインの色選びも重要で、黒よりもダークブラウンやグレーなど、肌や髪の色になじみやすい控えめな色を選ぶのが賢明です。
これらの色であれば、ラインを引いても悪目立ちせず、目元に自然な奥行きを与えることができます。
悲しみに寄り添う控えめな目元の表現
葬儀の場では、目元は特に感情が出やすい部分です。
涙を流すこともあれば、悲しみやつらさから目が赤くなったり、腫れぼったくなったりすることもあります。
このような状況で、派手なアイメイクをしていると、かえって不自然に見えてしまいます。
悲しみに寄り添う目元を表現するためには、アイラインは「あくまでも目元のフレームを自然に整える」という意識で使うことが大切です。
目尻を跳ね上げたり、太く濃いラインを引いたりするのは避けましょう。
これらの引き方は、目を大きく見せる効果はありますが、同時に強い印象を与えてしまい、悲しみの場にはふさわしくありません。
理想的なのは、「アイラインを引いているかどうか分からないくらい、自然に目元が引き締まっている」状態です。
例えば、まつ毛の隙間を埋めるように、点々と細かくラインを乗せていく方法や、まつ毛の生え際ギリギリに、ごく細い線を引く方法があります。
これにより、目の輪郭が少しはっきりし、目元がぼやけるのを防ぎつつも、強い印象を与えることはありません。
色も、漆黒のアイライナーよりも、ダークブラウンやグレーといった、柔らかい印象の色を選ぶのがおすすめです。
これらの色は、目元に自然な影を作り出し、深みを与える効果がありますが、黒ほど主張が強くありません。
目元全体の色味を抑え、あくまでも自然な血色感を意識したチークやリップとバランスを取ることも大切です。
自然で控えめな印象に仕上げるアイラインの具体的な引き方
葬儀メイクにおけるアイラインは、いかに自然に見せるかが鍵となります。
普段のメイクのように目力を強調するのではなく、あくまでも「疲れて見えがちな目元を少しだけ引き締め、顔色を悪く見せない」ことを目的とします。
具体的な引き方としては、太く濃いラインは避け、まつ毛の生え際に沿って細くラインを入れる「インサイドライン」や、まつ毛の隙間を点で埋める「点置き」がおすすめです。
これらの方法は、目の輪郭を自然に際立たせつつ、ラインを引いていることが分かりにくいため、葬儀の場にふさわしい控えめな目元を演出できます。
使用するアイライナーの色は、黒でも構いませんが、より自然に見せたい場合はダークブラウンやグレーを選ぶと良いでしょう。
ペンシルタイプやジェルタイプのアイライナーは、リキッドタイプに比べて柔らかく、自然な仕上がりになりやすいため、葬儀メイクに適しています。
特にペンシルタイプは、芯が柔らかすぎると滲みやすいという難点はありますが、細く丁寧に引くことで、まつ毛の根元に自然になじませることができます。
ジェルタイプは密着度が高く崩れにくいという利点がありますが、乾くのが早いため、素早く修正する必要があるかもしれません。
どちらのタイプを選ぶにしても、「いかに線を引いているように見せないか」を意識することが重要です。
目尻は目の形に沿って自然に終わらせるか、長く引きすぎないように注意しましょう。
失敗しない!基本のナチュラルラインと隠しライン
葬儀メイクでのアイラインで失敗しないためには、まず基本のナチュラルラインの引き方をマスターしましょう。
最も自然に見えるのは、まつ毛の生え際、特にまつ毛とまつ毛の間の隙間を埋めるようにラインを引く「インサイドライン」です。
鏡を見ながら、まつ毛の根元を少し持ち上げるようにして、粘膜に近い部分に細くラインを入れていきます。
この時、一気に線を引こうとするのではなく、短いストロークで少しずつ埋めていくのがコツです。
これにより、まつ毛の密度が高まったように見え、自然に目元が引き締まります。
さらに自然に見せるテクニックとして、「隠しライン」があります。
これは、まつ毛の隙間を点で埋めていく「点置き」のことです。
アイライナーのペン先やブラシを使って、まつ毛の根元の隙間に点々と色を置いていきます。
これにより、まるでアイラインを引いていないかのように見えるのに、目元がほんの少しだけ強調され、顔色が良く見えます。
この方法は、アイラインを引くのが苦手な方でも簡単に試せるのでおすすめです。
使用するアイライナーの色は、黒よりもダークブラウンの方がより自然になじみます。
あくまでも「隠す」ラインなので、太さや濃さは最小限に留めましょう。
下まぶたや目尻のアイラインはどこまで?
下まぶたのアイラインは、目を大きく見せる効果があるため、普段のメイクで取り入れている方も多いかもしれません。
しかし、葬儀という場においては、下まぶたにアイラインを引くことは基本的には避けるべきです。
下まぶたのラインは、上まぶたに比べて目立ちやすく、濃く見えがちです。
また、涙を流す可能性が高い場では、下まぶたのアイラインは特に滲みやすく、崩れてしまうと顔全体が汚れた印象になってしまうリスクがあります。
もし、どうしても下まぶたに何か加えたい場合は、アイライナーではなく、同系色のマットなアイシャドウを細いブラシにとり、目尻側のごく一部に淡く影を入れる程度に留めましょう。
これでも、下まぶたが少し引き締まり、目元がぼやけるのを防ぐことができます。
目尻のアイラインについても、普段のように長く跳ね上げたり、角度をつけたりするのは避けてください。
葬儀メイクでは、目のフレームラインに沿って自然に終わらせるのが最もふさわしい引き方です。
目尻を少しだけ延長したい場合でも、長くても数ミリ程度に留め、角度はつけずに目のカーブに沿わせるようにします。
「引いているか分からないくらい」が理想であり、目尻のラインが主張しすぎないように注意しましょう。
涙にも負けない!崩れにくいアイラインの選び方と対策
葬儀という場では、悲しみから涙を流す可能性が非常に高いです。
そのため、メイク崩れ、特にアイラインの滲みは大きな悩みの種となります。
涙でアイ