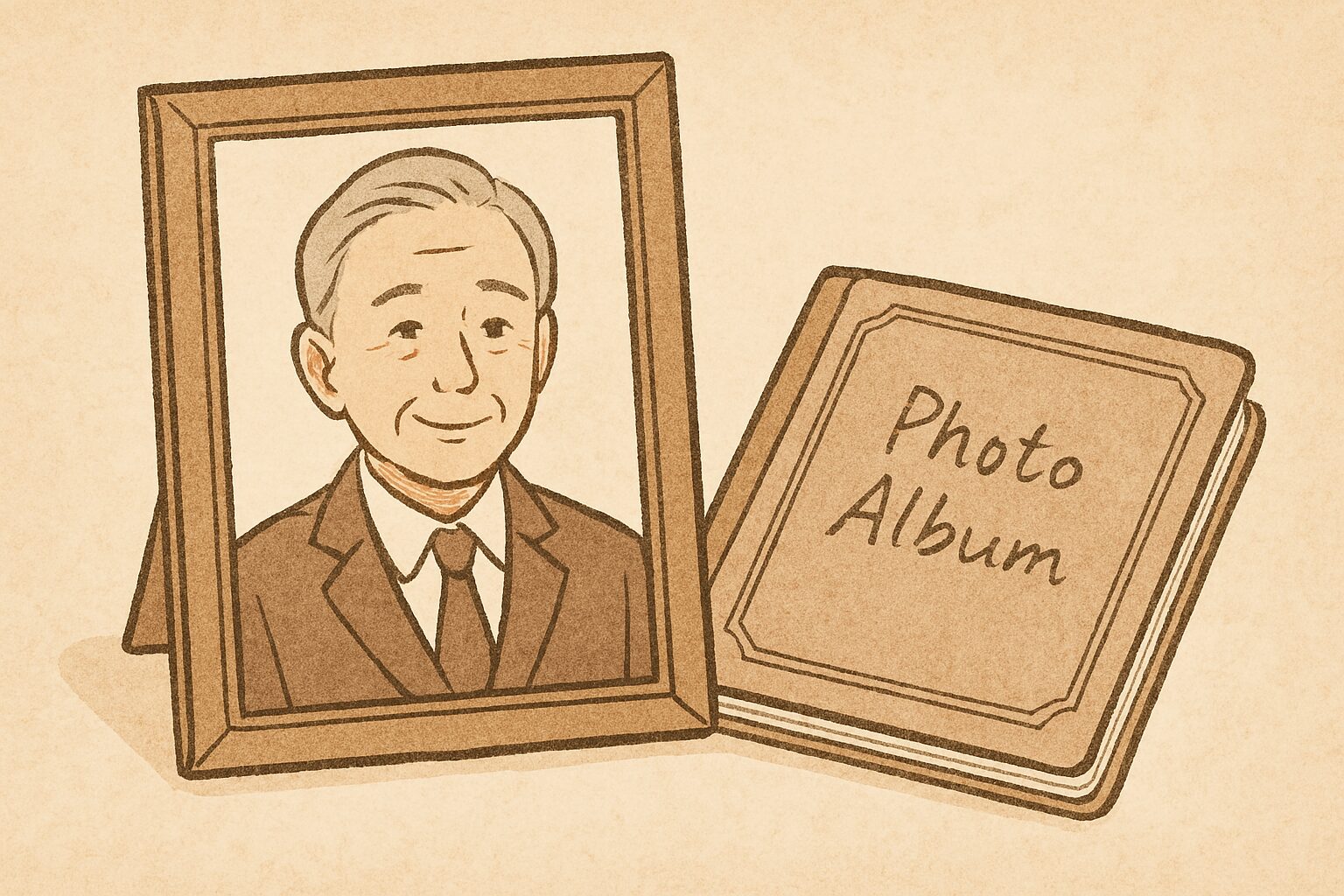「生前葬儀」という言葉を聞いたことがありますか?もしかすると、「生きているのにお葬式?」と少し不思議に思うかもしれません。
かつて葬儀といえば、故人を見送るための儀式が一般的でした。
しかし、価値観の多様化や終活への関心の高まりとともに、自分自身の生きている間に感謝を伝えたり、人生の節目を祝ったりする「生前葬儀」を選ぶ人が増えています。
この記事では、生前葬儀とは一体どのようなものなのか、その目的から、あなたが検討する際に知っておくべきメリットとデメリット、そして具体的な進め方や費用について、分かりやすく丁寧にご紹介します。
自分らしい最期、そしてその前の人生をどう締めくくりたいか、考えるきっかけになれば幸いです。
生前葬儀とは?従来の葬儀との違いと広がり
生前葬儀とは、文字通り、本人が生きているうちに行う葬儀、あるいはそれに類するお別れや感謝の会を指します。
一般的な葬儀が、故人の冥福を祈り、遺族や友人が故人を偲ぶ儀式であるのに対し、生前葬儀は、本人が主体となり、自身の人生を振り返り、お世話になった方々へ感謝の気持ちを伝えたり、友人知人との親睦を深めたりする目的で行われることが大きな特徴です。
宗教的な儀式というよりも、人生の集大成としてのイベントやパーティーに近い形式で行われることも多く、その内容は主催者である本人の意思や希望が色濃く反映されます。
従来の葬儀は、亡くなった後、短い時間の中で遺族が故人の意思を推し量りながら準備を進めなければなりません。
悲しみの中で多忙な手続きや準備に追われることも少なくありません。
一方、生前葬儀は、本人が元気なうちに、十分な時間をかけて企画・準備できるため、細部にわたって自分のこだわりや希望を反映させやすいという利点があります。
誰を招くか、どのような雰囲気の会にしたいか、どんな音楽を流したいか、どんな料理を提供したいかなど、すべて自分で決めることができるのです。
近年では、終活の一環として、自身の死後に関する準備と並行して生前葬儀を計画する人も増えており、その形式も多様化しています。
ホテルでの立食パーティー形式や、思い出の場所に集まって行う会、趣味をテーマにしたイベント形式など、自由な発想で企画されています。
なぜ今、生前葬儀を選ぶ人が増えているのか
生前葬儀を選ぶ人が増えている背景には、いくつかの理由が考えられます。
一つは、人生の最期を自分でプロデュースしたい、という意識の高まりです。
核家族化や人間関係の変化により、従来の形式的な葬儀に縛られたくない、あるいは、家族に負担をかけたくないという思いから、自分の意思で準備を進められる生前葬儀を選択する人が増えています。
また、SNSなどで個人のライフスタイルや価値観を発信する機会が増えたことも影響しているかもしれません。
自分らしい生き方を追求する中で、自分らしい「旅立ち方」や「お別れの仕方」を模索する人が増えているのです。
さらに、「感謝を伝えたい」という強い思いも、生前葬儀を選ぶ大きな動機となっています。
従来の葬儀では、亡くなった後に故人の功績や人柄が語られますが、本人が直接「ありがとう」を伝える機会はありません。
生前葬儀であれば、お世話になった方一人ひとりの顔を見ながら、直接感謝の言葉を伝えたり、思い出話に花を咲かせたりすることができます。
これは、参列者にとっても、故人との最後の対話や交流の機会となり、深い感動や喜びをもたらすことがあります。
ある生前葬儀では、参加者全員に手書きのメッセージカードを配り、一人ひとりに言葉をかけて回ったという方もいました。
そうした温かい交流は、従来の葬儀ではなかなか実現できないことです。
加えて、終活の一環として、自身の死後の準備をスムーズに進めたいという実用的な理由もあります。
生前葬儀を行うことで、自身の交友関係を整理したり、家族が把握しきれていない人間関係を共有したりする機会にもなります。
また、自身の葬儀や遺産に関する希望を事前に伝えておくことで、残された家族が迷ったり、負担を感じたりすることを減らすことができます。
エンディングノートに生前葬儀の希望を詳しく書き記しておくことで、より具体的に計画を進めることが可能です。
これらの理由が複合的に絡み合い、生前葬儀という選択肢が多くの人々に受け入れられつつあります。
形式にとらわれない自由なスタイルとは
生前葬儀の最大の魅力の一つは、その形式の自由さです。
従来の葬儀のような厳格なルールやしきたりに縛られる必要がありません。
主催者である本人が、どのような目的で、誰に集まってほしいか、どのような時間を過ごしたいかを自由にデザインできます。
例えば、音楽が好きな人であれば、自身の好きなアーティストの曲を流したり、ミニコンサートを開いたりすることも可能です。
旅行が好きだった人であれば、思い出の旅先をテーマにした装飾を施したり、ゆかりのある料理を提供したりするのも良いでしょう。
ある方は、自身の趣味である写真の個展を会場の一角で開き、集まった人々に自身の作品を見てもらいながら語り合う会にしたそうです。
会場も、葬儀会館である必要はありません。
ホテルやレストランの宴会場、公民館、カフェ、自宅、さらには屋外の公園や庭園など、本人の希望や会の趣旨に合わせて自由に選ぶことができます。
服装も、喪服である必要はなく、平服や、テーマに合わせた衣装など、自由に設定できます。
参列者にもドレスコードを指定することもあります。
プログラムも、お経や焼香といった宗教的な儀式を一切含まない、純粋な交流の場とすることも可能です。
思い出のスライドショーを上映したり、参加者からメッセージをもらったり、本人がスピーチをしたりと、内容は多岐にわたります。
このように、生前葬儀は「こうでなければならない」という固定観念がなく、まさに「自分らしさ」を最大限に表現できる場となります。
これは、人生の最期を自分自身の言葉で締めくくりたい、感謝の気持ちを形にしたいと願う人々にとって、非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。
形式にとらわれず、心から望む形で大切な人々との時間を過ごせることこそが、生前葬儀が持つ大きな価値なのです。
ただし、自由であるからこそ、企画・準備には時間と労力がかかります。
どのような会にしたいのか、しっかりとイメージを固めることが重要になります。
生前葬儀を行う目的と、あなたが得られるメリット
生前葬儀を行う目的は人それぞれですが、共通するのは「生きているうちに」という点です。
この「生きているうちに」行うからこそ得られる、従来の葬儀にはない特別な目的やメリットがあります。
それは、単に形式的な儀式を行うのではなく、自分自身が主体となって、人生の集大成として、あるいは大切な人々への感謝の表明として、意味のある時間を創造できるということです。
この目的を達成することで、主催者自身だけでなく、参列者にとっても忘れられない経験となることが多いのです。
具体的には、自分の意思を明確に反映させられること、大切な人々に直接感謝を伝えられること、そして残される家族の負担を軽減できることなどが挙げられます。
従来の葬儀は、とかく形式やしきたりに追われがちで、故人の人柄や人生が十分に反映されないことも少なくありませんでした。
また、遺族は悲しみの中で様々な決定を迫られるため、精神的、肉体的に大きな負担を抱えることになります。
生前葬儀は、これらの課題を解決し、よりポジティブで前向きな形で人生の節目を迎えるための手段となり得ます。
例えば、ある方は、自身の趣味である俳句の会を兼ねた生前葬儀を開催し、参加者と一緒に句会を楽しんだそうです。
このように、自分の「好き」や「大切にしていること」を前面に出すことで、集まる人々との絆を再確認し、豊かな時間を共有できるのです。
生前葬儀の目的は、単なる「お別れ」の予行演習ではなく、むしろ「生」を祝い、感謝を分かち合うことにあると言えるでしょう。
自分の意思を反映できる自由なスタイル
生前葬儀の最大のメリットの一つは、すべてを自分の意思で決定できるという点です。
どのようなテーマにするか、誰を招待するか、会場はどこにするか、どのようなプログラムにするか、どのような料理を用意するか、BGMは何にするか、服装はどうするかなど、細部にわたるまで自分のこだわりを反映させることができます。
これは、自分の人生を自分で締めくくる、究極の自己表現とも言えます。
例えば、派手なことが好きな人であれば、エンターテイメント性の高い華やかなパーティー形式にするかもしれませんし、静かに語り合いたい人であれば、こじんまりとした会食形式にするかもしれません。
従来の葬儀では、遺族が故人の生前の意思を推測して形式を決めたり、地域の慣習に従ったりすることが一般的です。
しかし、生前葬儀であれば、本人が直接希望を伝え、それを実現することができます。
「私はこんな人生を送ってきました」「こんな人たちに囲まれて幸せでした」というメッセージを、自分の言葉で、自分の望む形で発信できるのです。
これは、自分自身の人生に対する深い肯定感につながり、残りの人生をより前向きに生きる力となることもあります。
ある男性は、生前葬儀で、自身の人生のターニングポイントとなったエピソードを語り、集まった友人や家族に感謝を伝えました。
その会は、参加者にとって彼の人生を深く知る貴重な機会となり、彼自身も「やり残したことはない」と清々しい気持ちになれたそうです。
この自由なスタイルは、既存の形式にとらわれずに、本当に自分が大切にしている価値観を表現できるという点で、他のどのような儀式にも代えがたい魅力を持っています。
ただし、自由であるがゆえに、ゼロから企画を考えなければならない大変さもあります。
しかし、そのプロセス自体が、自分の人生を振り返り、整理する貴重な時間となるでしょう。
専門のプロデューサーや葬儀社に相談することで、アイデアを形にするサポートを受けることも可能です。
生きている間に感謝を伝えられる貴重な機会
生前葬儀の最も重要な目的の一つが、お世話になった方々へ、生きているうちに直接感謝の気持ちを伝えることです。
私たちは日々の忙しさに追われ、大切な人への感謝の気持ちを十分に伝える機会を逃してしまうことが少なくありません。
しかし、生前葬儀という場を設けることで、意図的に感謝を伝えるための時間と空間を創り出すことができます。
例えば、両親、配偶者、子どもたち、学生時代の友人、職場の同僚、趣味の仲間など、自身の人生に関わってくれた一人ひとりに、具体的なエピソードを交えながら「あの時は本当にありがとう」「あなたのおかげで今の私があります」と伝えることができます。
言葉だけでなく、表情や声のトーン、そして直接顔を見て話すことで、感謝の気持ちはより深く伝わります。
参加者も、感謝されることで自身の存在価値を再認識し、温かい気持ちになるでしょう。
ある女性は、生前葬儀で、若い頃に世話になった恩師を招き、当時の感謝を伝えました。
恩師は涙を流して喜んでくれ、その姿を見た彼女も深い満足感を得たそうです。
また、生前葬儀は、これまでゆっくり話す機会がなかった親戚や友人同士が交流する場ともなります。
自身の人生を振り返るスピーチを聞いてもらったり、思い出の品を展示したりすることで、参加者は主催者の人となりや人生について深く理解することができます。
これは、主催者が亡くなった後に、残された人々が故人を偲ぶ上での大切な礎となります。
生きているうちに感謝を伝え、人との繋がりを再確認できることこそが、生前葬儀がもたらすかけがえのない価値であり、多くの人が生前葬儀を選ぶ最大の理由の一つと言えるでしょう。
家族の負担を減らし、安心して旅立てる準備
生前葬儀を行うことは、残される家族の精神的・物理的な負担を大きく軽減できるという実用的なメリットも持ち合わせています。
人が亡くなった後、遺族は悲しみの中で、葬儀の準備、各種手続き、相続など、短期間に多くのことをこなさなければなりません。
特に葬儀に関しては、故人の意思が不明確な場合、遺族は故人の好みや希望を推測しながら、会葬者の範囲、葬儀の形式、会場、予算などを決定する必要があり、大きな精神的負担となります。
生前葬儀を計画・実行しておくことで、自身の希望するお別れの形を明確に伝えることができます。
誰に連絡してほしいか、どのような雰囲気で送ってほしいか、費用はどのくらいかけたいかなどを具体的に決めておくことで、遺族は迷うことなくスムーズに準備を進めることができます。
また、生前葬儀で自身の交友関係を家族に紹介したり、エンディングノートに連絡先をリストアップしたりしておくことで、遺族が訃報を伝える際の負担も軽減されます。
あるご夫婦は、生前葬儀で親戚や友人を招き、配偶者や子どもたちにそれぞれの関係性を紹介しました。
これにより、万が一のことがあった際にも、家族が慌てずに連絡できるようになり、安心感が生まれたと言います。
さらに、生前葬儀である程度の区切りをつけることで、死後の葬儀をより小規模な家族葬や密葬にしたり、あるいは行わないという選択肢も現実的になります。
これにより、遺族は経済的な負担や、多くの会葬者への対応といった物理的な負担からも解放されます。
自分が元気なうちに準備を済ませておくことで、「残される家族に迷惑をかけたくない」という思いを実現できるのです。
これは、本人にとっても、最期を安心して迎えられるという大きな心の平安につながります。
生前葬儀は、自分自身のためだけでなく、愛する家族への最後の配慮とも言えるでしょう。
生前葬儀を検討する前に知っておきたいデメリットと注意点
生前葬儀には多くの魅力